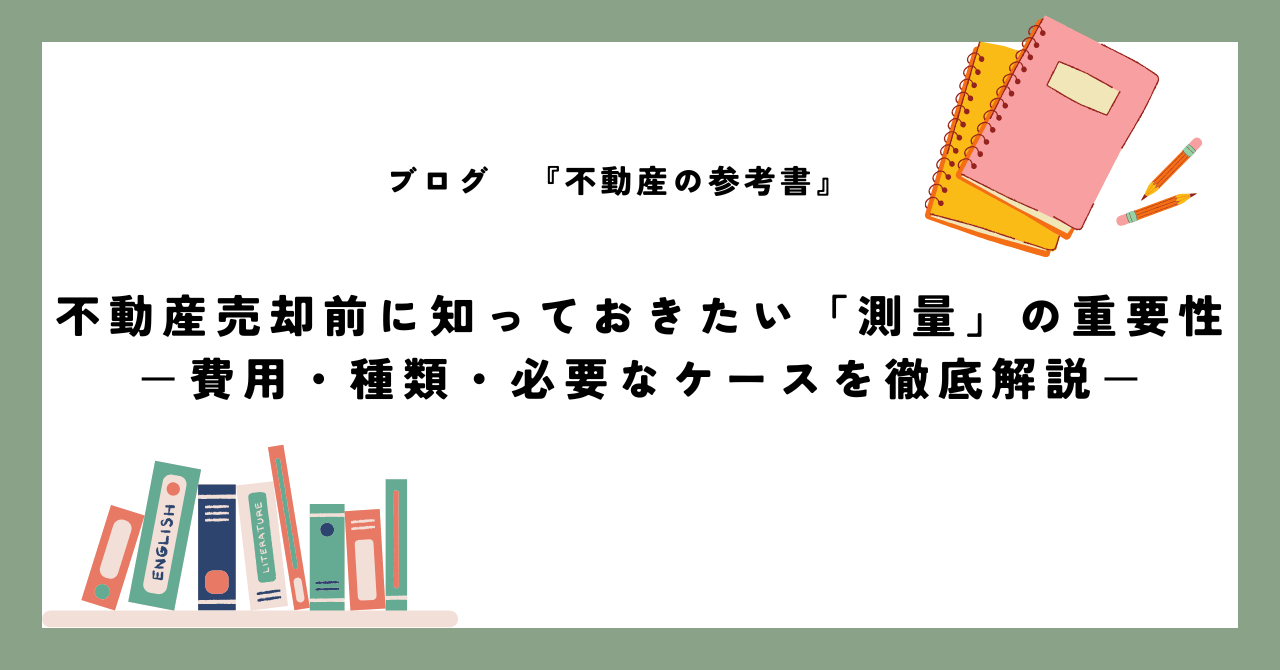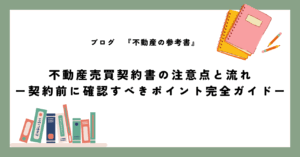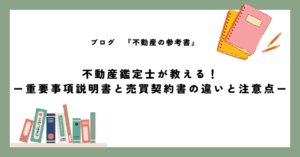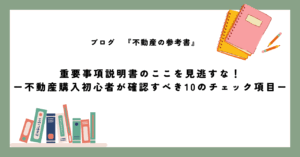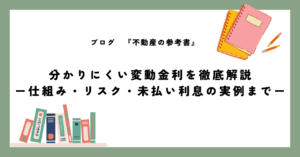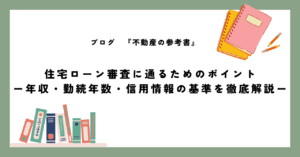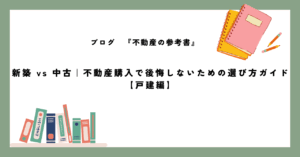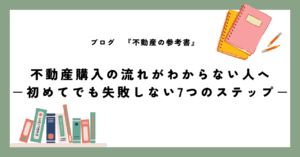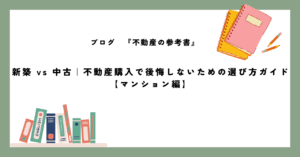不動産を売却する際、「まずは査定」と考える方は多いですが、実はその前に確認しておきたい大切なポイントがあります。それが「測量」です。
「自分の土地の広さは登記簿に書いてあるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、実際の取引の現場では、境界の不明確さや隣地とのトラブルにより、売却に支障が出るケースも少なくありません。
この記事では、不動産売却時における測量の役割や、なぜ必要なのか、どのような種類があるのか、費用はどれくらいかかるのかなど、初心者の方にもわかりやすく徹底的に解説します。売却をスムーズに、かつトラブルなく進めるための「測量の基礎知識」を身につけていきましょう。
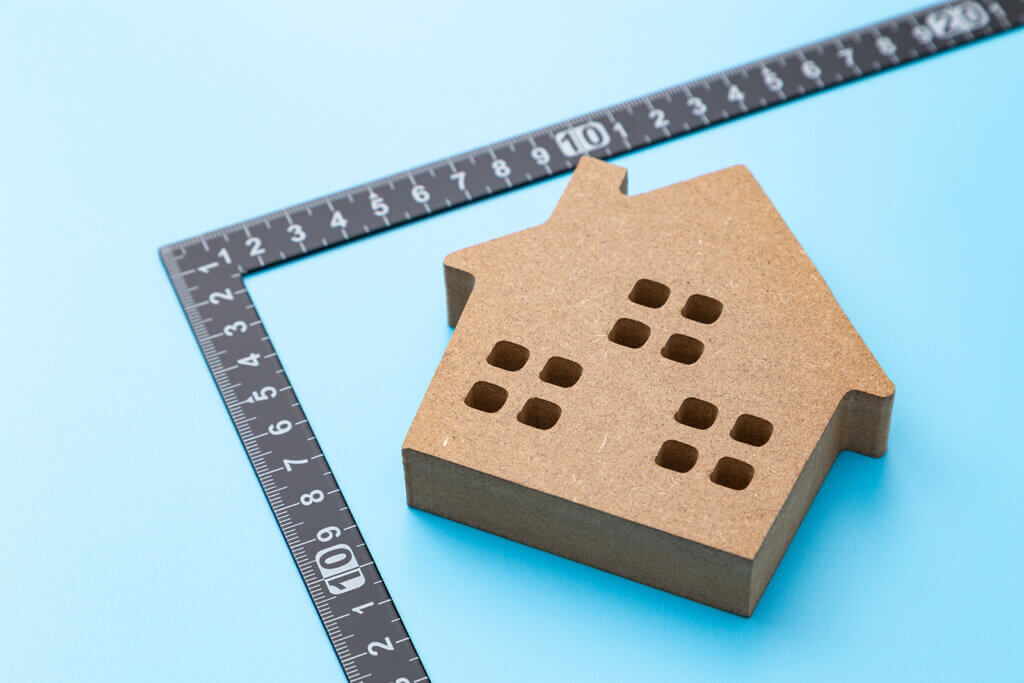
はじめに:なぜ不動産売却に測量が必要なのか
不動産を売却する際、何となく「測量」は必要と思われている方は多いかと思います。とくに土地や戸建ての売却時には、買主や仲介業者から「確定測量図はありますか?」と尋ねられることがあります。普段の生活で意識することのない測量ですが、実は売却の成否や価格に大きな影響を与える重要な要素なのです。
まず、不動産売却における「測量」とは何かを整理しましょう。簡単に言えば、測量とは土地の面積や境界を正確に測る作業です。売主が「この土地は100㎡です」と言っても、それが正確な数値でなければ買主にとっては大きなリスクになります。たとえば、実際の面積が98㎡だった場合、その差2㎡は価格にして数十万円、場合によっては百万円単位の違いを生み出す可能性もあるのです。
また、隣接地との境界が不明確なまま売却を進めると、売買契約後に隣地所有者とのトラブルに発展するリスクがあります。買主としても、将来的な境界紛争を避けたいと考えるため、測量によって「境界が明確であること」が安心材料になります。
さらに、42条2項道路、指定建築線等による「セットバック」の有無や、道路との接道状況なども査定価格の重要な判断材料になりますが、これらも正確な測量がなければ判断が困難となることもあります。つまり、測量は不動産の「正確な価値」を明らかにするための第一歩であり、売主と買主双方のリスクを減らすための基盤といえるのです。
不動産取引の現場では、以下のようなケースで測量の必要性が特に高まります。
- 売却する土地が相続によって取得された場合(古い測量図しかない)
- 登記簿上の面積と実測の面積が大きく異なる疑いがある場合
- 隣地との境界杭が見当たらない、または境界紛争があった過去がある場合
- 建物を解体して更地として売却する場合
- 土地分筆(複数に分けて売却)を検討している場合
このような状況では、売却前にしっかりと測量を行うことで、円滑な取引と適正価格での売却を実現することができます。
本ブログでは、こうした測量の基礎知識から、種類・費用・注意点・売却への影響まで、測量と不動産売却の関係を幅広く解説していきます。「測量が必要なのは分かったけど、どこまでやればいいの?」「費用はどれくらいかかる?」「誰に頼めばいいの?」といった疑問にお応えできる内容を網羅しています。
これから不動産を売却しようとしている方にとって、測量に関する正しい知識を持つことは、自身の資産を適切に守り、有利に売却するために欠かせないステップです。まずは「なぜ測量が必要なのか」をしっかり理解し、次章以降で具体的な内容を掘り下げていきましょう。

測量が必要になる主なケース
不動産売却の際、すべての土地に測量が必要な訳ではありません。しかし、測量を行うことでトラブルを未然に防ぎ、円滑な売却を実現できるケースは数多くあります。とくに以下のようなケースでは、測量が強く推奨される、もしくは実質的に必須とされることもあります。
ここでは、測量が必要とされる代表的なケースを5つ紹介し、それぞれの背景と注意点を詳しく解説します。
境界が未確定・境界標がない場合
まず最も基本的で重要なのが、「境界が明確でない」場合です。
境界標とは、土地の境界を示すコンクリート杭や金属プレートなどの目印で、これが全ての境界点に打たれていれば、その土地の境界が明確であると判断できます。しかし実際には、以下のような事情により境界標が存在しない、あるいは不完全な状態であることが多くあります。
- 古い杭が失われている
- 自然災害や工事で杭がずれた
- そもそも過去に境界を確定していなかった
境界標が不明確なままでは、隣地所有者との立ち合いや合意を得ることが難しくなり、買主も安心して土地を購入できません。売買後のトラブルを防ぐためにも、境界が不確定な場合は、土地家屋調査士による「境界確定測量」を行う必要があります。
古い土地や相続で取得した土地
相続によって取得した土地や、長年にわたって利用してきた「古い土地」では、登記情報と現況が一致していないケースがよくあります。
例えば、
- 昭和初期の測量図が使われている
- 分筆や合筆を経ているが記録が不明
- 所有者変更が繰り返され、現況と整合していない
こうしたケースでは、土地の面積や形状、境界線の正確な情報が不明なため、売却時に「正確な評価ができない」問題が生じます。加えて、相続人間での共有状態や境界認識の食い違いがあると、境界トラブルが売却の妨げになる可能性もあります。
古い土地ほど「現況確認のための測量」が求められることを覚えておくべきです。
隣地との境界トラブルがある場合
近隣との関係が円満であっても、土地の境界が明確でない場合には、誤解や思い違いからトラブルが起きることがあります。以下のような事例は非常に多く見られます。
- 塀やブロックが隣地に越境している
- 古くからの慣習で勝手に境界を認識していた
- 隣地所有者が異なる主張をしている
このような境界に関する紛争や認識のズレがある場合は、必ず第三者(土地家屋調査士など)の立ち会いのもと、正確な測量を行い、両者の合意を得る必要があります。境界確認書や筆界確認書を作成しておくことで、将来的なトラブルの回避にもつながります。

地積(面積)が実際と登記で異なる、公図と形状が異なる場合
売却時に提示される土地面積は、「登記簿に記載された地積」に基づいて行われることが多いです。また、公図も同様です。しかし、実際に測ってみると、
- 登記より実際の面積が狭い
- 図面の縮尺や測量方法が古く、誤差がある
- 公図と実際の土地形状が異なる
といったことが判明するケースもあります。
このような相違があるまま売却を進めると、契約後の売買金額の減額交渉やクレーム、最悪の場合には契約解除に至る可能性もあります。特に登記面積を基に価格交渉をしていた場合は、買主にとって重大な問題となるため、事前の測量により正確な面積を把握しておくことが肝心です。
分筆や開発予定がある場合
分譲地として、土地を区分けして売却する予定がある場合、土地の一部を分筆して、住宅用地などとして開発する予定がある場合には、必ず「確定測量」が必要になります。
このようなケースでは、以下のような理由で測量が求められます。
- 法務局で分筆登記を行うために境界確定が必要
- 建築確認申請の際に面積・接道の証明が求められる
- 土地利用区分(農地→宅地など)の変更要件を満たすため
とくに開発を前提とした不動産売却や取引では、測量図がなければ不動産会社側も価格を出しにくく、売却までに時間がかかる要因となります。将来的に開発を検討している場合も、事前の測量によって土地の価値と可能性を最大化することができます。
測量は「余計な出費」ではなく「将来への備え」
測量にかかる費用や時間を理由に、測量を敬遠する売主も少なくありません。しかし、境界が不明確な土地は「安心して買えない土地」と見なされ、売却において明らかに不利になります。
また、トラブルや再交渉のリスクを防ぐ意味でも、事前の測量は費用対効果の高い投資です。必要な場面で的確に測量を行うことは、不動産売却を成功させる第一歩と言えるでしょう。

測量が不要なケース
次に進む前に、不動産売却に際し、測量が不要なケースも説明しておきましょう。
分譲地
分譲地は、開発の際に、測量の上、分筆等の手続がされていますので、余程古く開発されたのでなければ、測量は不要となるケースが多いです。
マンション
マンションは、持分として土地を所有していますが、実質的には建物部分の取引となりますので、土地の測量は不要です。
通常は、マンション建築の際に、測量は済んでいる筈です。
測量の種類とその特徴
不動産売却において「測量が必要」と言っても、その測量の種類は一つではありません。測量には目的や状況に応じていくつかの種類があり、それぞれに特徴や費用、所要日数などが異なります。ここでは、不動産売却時によく用いられる代表的な測量の種類について、詳しくご紹介します。
現況測量
最も基本的な測量が「現況測量」です。これは、現在の土地の状況を調査し、建物や塀、道路、隣地との境界線などを図面に落とし込むものです。隣地所有者と立会いを行わない点で、後の確定測量とは異なります。
特徴
- 境界確定の法的効力はない
- 売買契約前の現状把握に有用
- 隣地所有者の立会い不要
- 費用は比較的安価(20万円前後〜)
- 実施期間:1〜2週間程度
使用される場面
- 不動産取引の前準備
- 建築設計・施工のための基礎資料
- 土地の境界確認・トラブル防止
- 開発行為や造成工事の計画
- 行政手続きや申請書類の添付資料
- 災害後の復旧・再建計画
- 後に説明する確定測量が困難な場合
境界確定測量(確定測量)
売却後のトラブルを避けるため、不動産売買においては、法的な「確定測量」を行うことが推奨されます。これは隣接地の所有者と立会いの上、土地の境界を明確にし、公的に証明する測量です。
但し、隣地所有者との立ち合いが必要となるため、時間がかかることもあり、最悪の場合、境界を確定できないこともあることに、注意する必要があります。
特徴
- 境界が法的に確定する
- 隣接地所有者全員との立会いが必要
- 登記や分筆の前提となる
- 成果品として「境界確定図」が作成される
- 費用は高め(40万円〜100万円程度)
- 実施期間:1〜2ヶ月(立会い調整に時間がかかる)
使用される場面
- 土地売却時に面積を正確に把握したい
- 分筆して売却する場合
- トラブル防止を重視したい場合
確定測量が不要となるケース
不動産売却の際に、必須とも言える確定測量ですが、以下の場合には、確定測量をしなくても売却できることがあります。
- 業者に買い取ってもらう場合
- 希少性の高い立地に存する場合
業者に買い取ってもらう場合には、確定測量は、後に業者の方で実施しますので、売主の方で、実施しなてくもいい場合があります。ですが、業者に買い取ってもらう場合には、価格がその分安くなってしまうことに留意して下さい。
もう一つの希少性の高い立地の場合です。なかなか売り物件が出ないような場所や、人気の高いエリアでは、確定測量が済んでいなければ購入しない、などと言っていたら、なかなか購入出来ません。
ですので、このような立地に存する場合には、確定測量を行わないでも売却することが可能となることがあります。
分筆測量
一筆の土地を複数に分けて売却したい場合に行われるのが「分筆測量」です。境界確定を前提に、新たな筆を登記するための測量です。
特徴
- 境界確定測量とセットで行われる
- 測量後、法務局への分筆登記が必要
- 開発・相続・売却などの場面で活用される
その他の測量(ドローン測量・GPS測量など)
近年では、技術の進歩によりドローンやGPSを活用した測量も登場しています。これらは広大な土地やアクセス困難な土地において効率的な測量が可能です。
これらは、境界確定は行いませんので、現況測量の一種と考えてもらって大丈夫です。
特徴
- 精度の高い3Dデータ取得が可能
- 大規模な土地に適する
- 費用や納期は個別案件により大きく異なる

まとめ
売却時に行う測量は「現況測量」で済むケースもあれば、「境界確定測量」や「分筆測量」など、より正確性や法的裏付けが求められるケースもあります。土地の状態や売却方法、将来のリスクを踏まえ、適切な測量方法を選ぶことが重要です。測量の種類によって費用・時間・手続きが大きく変わるため、早めに専門家に相談するのが成功への第一歩となります。
測量の流れ
現況測量と確定測量について、それぞれ測量の流れを説明します。
現況測量の流れ
依頼・打ち合わせ
まず、測量を依頼する段階では、測量士との打ち合わせが行われます。依頼者の目的(建築計画、不動産売買、開発行為など)に応じて、測量範囲や必要な精度、納期などを確認します。測量士は、現地の状況や過去の資料の有無などもヒアリングし、測量計画を立てます。
現地調査
打ち合わせ後、測量士が現地に赴き、土地の状況を確認します。具体的には、以下のような項目をチェックします。
- 境界標の有無と状態
- 地形の起伏や高低差
- 測量する土地及び周辺に存する構造物(道路、建物、塀など)
- 隣地との関係性
この段階で、測量に必要な準備(草木の除去、障害物の確認など)も行われることがあります。
測量作業
現地調査をもとに、実際の測量作業が行われます。使用される機器には、トータルステーション、GNSS(GPS)、レーザースキャナーなどがあり、土地の形状や高低差を正確に測定します。
測量士は、複数の測点を設定し、それぞれの座標を取得します。必要に応じて、隣地との境界線や道路との接道状況も記録します。測量作業は、測量する土地の大きさ、天候や地形によって数時間から数日かかることもあります。
図面作成
測量データが取得されたら、次は図面の作成です。現況測量では、主に以下のような図面が作成されます。
- 現況図(敷地図):土地の形状、面積(参考値)、構造物の位置などを記載
- 高低差図:地盤の起伏を示す図面
- 接道図:道路との関係を示す図面
これらの図面は、建築設計や開発計画の基礎資料として活用されます。
報告・納品
最後に、測量結果を依頼者に報告し、図面を納品します。報告書には、測量の概要、使用機器、測定精度、注意点などが記載されることが一般的です。
納品された図面は、建築士や不動産業者、行政機関などに提出され、次のステップへと進みます。
確定測量の流れ
立ち合いが必要となることを除けば、現況測量とほぼ同じです。
測量士への依頼と事前準備
まずは、専門家である土地家屋調査士に依頼します。依頼時には、土地の場所や面積、隣地との関係、過去の測量履歴などを確認し、測量の目的や範囲について相談します。調査士は、法務局や市役所から公図や登記簿、過去の測量図面など必要な資料を集め、事前調査を行います。
これは、先の現況測量とは変わりません。
現地調査と仮測量
資料をもとに、実際に現地へ赴いて仮測量を実施します。既存の境界標や土地の形状、構造物の位置などを確認し、仮の境界線を設定します。不明点があれば、資料と現地の状況をもとに最適な境界案を作成します。
隣地所有者との立会い
仮測量の結果をもとに、調査士が隣地所有者と連絡・調整し、現地で立会いを行います。その場で境界案を説明し、お互いに納得できれば合意し、境界標(杭など)を設置します。合意内容は「境界確認書」にまとめ、双方が署名・押印します。
図面・書類の作成と納品
合意した内容にもとづき、「確定測量図」や「境界確認書」など正式な図面と書類が作成されます。これらは不動産登記や売買契約の際に重要な資料となります。調査士は、これらの成果品を依頼者に納品し、必要に応じて法務局への登記手続きのサポートも行います。

測量によって生じるメリットとトラブル回避事例
測量というと、「費用がかかる」「手間がかかる」といった印象を持つ方も少なくありません。しかし、実際には土地売却や相続、開発、賃貸など、あらゆる不動産取引において“測量しておいて良かった”という事例は非常に多くあります。正確な測量は、不動産の価値を正当に評価し、トラブルを未然に防ぐ「保険」とも言える存在です。
この章では、測量を行うことによって得られる具体的なメリットと、実際にあったトラブル回避の事例についてご紹介します。
測量によって得られる主なメリット
土地の正確な面積・形状が把握できる
登記上の面積と実際の面積が異なるケースは珍しくありません。特に古くからの宅地や農地などでは、実測すると数㎡の差が出ることもあります。売却や相続時にこのズレが発覚すると、価格や分配に大きな影響が出る可能性があります。
メリット例:
- 実際の面積が登記より広く、価格アップにつながった
- 道路後退部分を事前に確認でき、建築計画に役立った
境界トラブルを防げる
「隣地との境界線があいまい」「塀やフェンスが境界を越えているかも」といった不安を感じたことがある方は多いでしょう。測量によって境界を明確にしておくことで、将来的な隣地との紛争を防ぐことができます。
メリット例:
- 将来の建替えや売却時に隣人と揉めない安心感
- 隣地との境界立会いが済んでいることで、買主の信頼を得やすい
不動産の価値を正しく伝えられる
測量図があることで、買主や不動産会社は「この土地は安心して取引できる」と判断しやすくなります。特に、確定測量図がある場合は法的証拠力が強く、売却活動がスムーズに進む要因となります。
メリット例:
- 売却価格の根拠として買主を説得できた
- 金融機関の評価が上がり、融資がスムーズになった
相続・贈与・分筆時のトラブルを防止
測量を行わずに相続や贈与を行うと、後になって「どこからどこまでが誰の土地か」で揉める原因になります。特に兄弟や親戚間での共有持分の分割では、測量図がないことで感情的な対立に発展するケースもあります。
メリット例:
- 相続人全員が納得する形で公平に分筆できた
- 税務署への申告時に根拠資料として評価が認められた
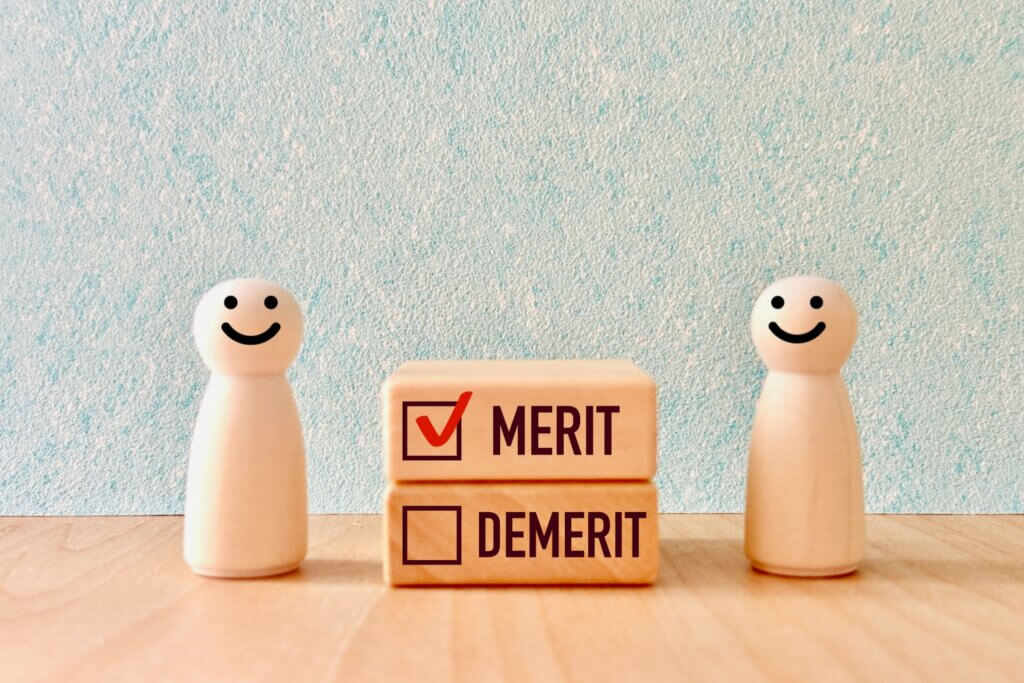
測量がなかったことで起きたトラブル事例
ここでは、測量を行わなかったことで実際に生じたトラブル事例をいくつか紹介します。
登記面積と実測面積の大幅な差による価格交渉の破談
都内のある土地で、登記簿上の面積が150㎡とされていたため、それを前提に売却活動を行っていました。しかし、契約直前に買主側が実測を依頼したところ、実際は約140㎡しかありませんでした。10㎡の差により価格の見直しを迫られ、売主側が納得できず契約が白紙になってしまいました。
対策:
事前に売主側で実測しておけば、価格交渉や契約の信頼性を高められた可能性が高いです。
隣地との境界トラブルで再建築がストップ
相続で取得した土地を更地にして建物を建てようとしたが、古いブロック塀が境界を越えている可能性があると指摘され、隣地との協議が必要になしました。境界確認書がなく、隣人との交渉が難航。結果、着工までに半年以上かかり、建築費用も当初予算を大幅にオーバーしてしまいました。
対策:
売却や建替え前に確定測量を行っておくことで、境界問題をスムーズに処理できた筈です。
相続人間での土地分割をめぐる対立
郊外の土地を3人の兄弟で相続しましたが、形状がいびつで、誰がどの部分を取得するかでもめてしまった。現況測量のみだったため、分筆登記が進まず、結果的に売却までに2年近くを要しました。
対策:
分筆を前提とした確定測量を早期に行い、相続人全員が納得する形を示すことが重要だったと思います。
測量による「安心」と「納得」は何よりの資産価値
以上のように、測量は単なる技術作業ではなく、「不動産という資産をトラブルから守るための盾」であり、取引をスムーズに進めるための「信頼の証明」でもあります。
費用や手間はかかりますが、それを上回る安心感と納得感を得られることが、多くの事例が分かると思います。
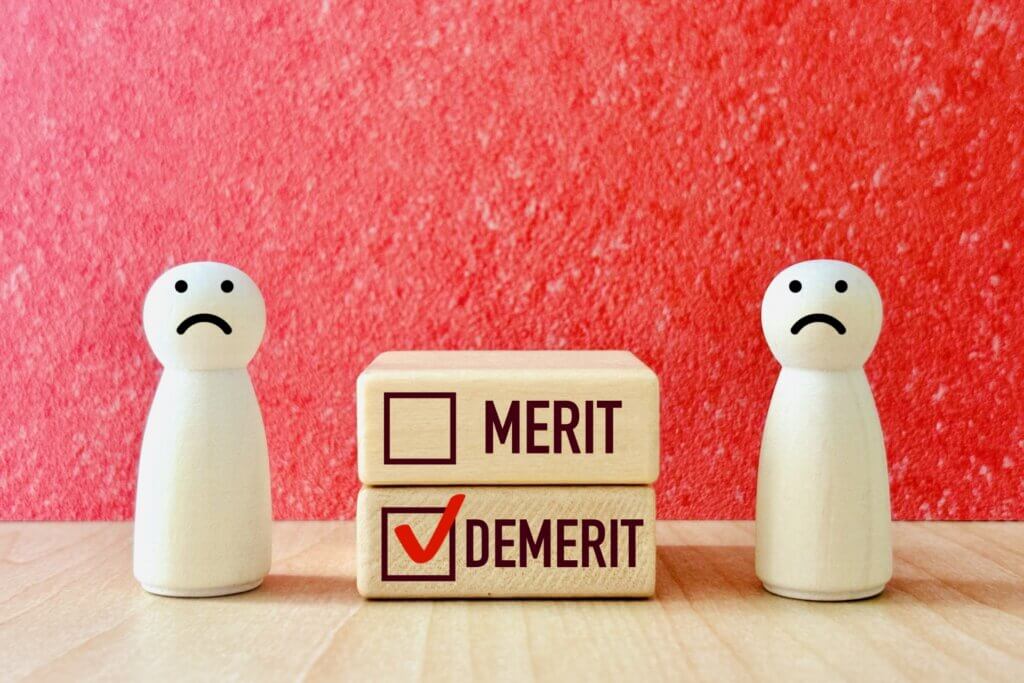
境界に関する法律とトラブル時の対応
不動産の売買・相続・開発・再建築など、あらゆる場面で重要となるのが「境界」の問題です。測量で明確になるのはこの“境界”ですが、そもそも境界とは何を指し、法律上どのように扱われているのか、また、隣地とのトラブルが生じたときにはどう対応すべきかを、具体的に見ていきましょう。
境界とは?法的な定義と種類
土地における「境界」とは、自分の土地と他人の土地の境目、つまり土地の所有権の限界線を意味します。
ただし、一般的に“境界”という言葉は以下のように複数の意味で使われています:
| 種類 | 概要 |
| 筆界(ひっかい) | 公法上の境界で、法務局に登記されている境界線。国家が定めたもので、個人間の合意では変更できません。 |
| 所有権界(しょゆうけんかい) | 実際に誰がどこまで所有しているかという私法上の境界。使用慣習や契約、時効取得などにより変わる可能性があります。 |
| 現況境界(げんきょうきょうかい) | 現在のブロック塀やフェンス、建物の位置など、目に見える境界のように見えるもの。必ずしも法的な境界とは一致しません。 |
このように、ひと口に「境界」といっても、法的な裏付けのある境界と、現況による目印とは別物であるため、正確な判断には専門的知識が不可欠です。

よくある境界トラブルと原因
不動産に関するトラブルの中でも、境界を巡る紛争は特に根深く、感情的な対立に発展するケースもあります。主なトラブル例は以下の通りです。
境界標(杭・石)が失われている
長年の経過で境界標がずれたり、撤去されたりしていると、境界位置が不明瞭に。これが発端となり、隣地との境界線をめぐる争いに発展することがあります。
現況と登記が異なる
古い宅地や農地では、現況(塀やフェンスの位置)と登記簿上の面積・形状が一致しないことがあり、「越境」や「不法占有」などが疑われる原因になります。
時効取得を主張された
20年以上、無断で隣地の一部を使用し続けた結果、「時効取得した」と主張されるケース。事前に測量・境界確認をしておけば防げた問題です。
再建築時の境界立会いでもめる
建替えをしようとしたときに、隣人の境界確認に同意が得られず、計画がストップ。場合によっては訴訟に発展することもあります。
境界トラブルの対応フロー
トラブルが発生した場合、いきなり弁護士や裁判に頼るのではなく、段階的に冷静な対応を取ることが重要です。
① 測量士・不動産鑑定士に相談する
まずは、状況を正しく把握するために専門家へ相談を。現況測量・登記調査を通じて、問題の本質を明らかにします。
② 境界確認を申し入れる(立会い)
隣地所有者との話し合いの場を設け、測量結果をもとに境界確認の立会いを依頼します。合意が得られれば「境界確認書」を取り交わすのが理想です。
③ 話し合いで合意できない場合はADRや調停へ
当事者同士の話し合いで解決できない場合は、法務局の筆界特定制度や、弁護士を通じた民事調停を活用します。裁判に比べて手続きが簡素で、費用も抑えられます。
④ 最終的には裁判(所有権確認訴訟・筆界確定訴訟)へ
話し合いでも調停でも決着しない場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。土地の所有権や境界線の位置が争点となり、専門的な主張立証が求められます。
トラブルを未然に防ぐための対策
境界をめぐるトラブルを未然に防ぐには、以下のような事前の対策が有効です。
- 確定測量を実施し、境界確認書を作成しておく
- 境界標を設置し、定期的に確認する
- 売却・相続・分筆時は、境界の確認を徹底する
- 隣人との良好な関係を築いておく(将来の協議がスムーズに)
特に、確定測量図の作成と境界確認書の保管は、不動産取引における重要な“安心材料”となります。測量士や不動産鑑定士の助けを借りて、記録に残しておくことが将来の大きなトラブル防止につながります。
境界の問題こそ、専門家の力を借りるべき分野
境界問題は、個人の経験や常識では判断が難しく、感情的な衝突も生じやすい分野です。法律・測量・権利関係が複雑に絡むため、不動産鑑定士や測量士、弁護士などの専門家の連携が必要となります。
「こんなことで相談してもいいのかな」と思われるような些細な疑問でも、早めに動くことで大きなトラブルを防ぐことができます。
11. 信頼できる測量士・専門家の選び方
不動産売却や相続、境界トラブルの解決において「測量士」や「不動産鑑定士」などの専門家の力は欠かせません。しかし、測量や鑑定は一般の方にはなじみが薄く、「どのように専門家を選べばいいのか分からない」という方も少なくありません。
ここでは、後悔のない不動産測量・評価を進めるために、信頼できる専門家を選ぶ際のポイントや注意点をわかりやすく解説します。
測量を依頼できる専門家とは?
測量を行うことができるのは、国家資格である「土地家屋調査士」と「測量士(補)」です。両者の違いを簡単に整理すると次のとおりです。
| 資格 | 主な業務 | 特徴 |
| 土地家屋調査士 | 登記に必要な測量・図面作成・境界確定業務 | 境界トラブルや登記の専門家 |
| 測量士/測量士補 | 測量法に基づく地形測量・基準点測量など | 公共測量や大規模開発の経験が多い |
不動産売却や境界確定を目的とする場合、土地家屋調査士に依頼するのが基本です。また、不動産鑑定士は、土地や建物の「適正な価格評価」に長けており、測量結果をもとに価格の裏付けを取りたい場合に有効です。
信頼できる専門家を選ぶ6つのポイント
① 実績や経験年数を確認する
境界確定や不動産売却は実務経験の差が結果に大きく影響します。過去の実績や担当件数を聞いてみましょう。たとえば、「過去3年で何件の確定測量を行ったか」などの具体的な情報は信頼性の指標になります。
② 地域に精通しているか
その土地の地歴や法務局の状況、役所の対応などを熟知している地元の専門家は、手続きを円滑に進めてくれる可能性が高いです。「○○市の測量に慣れているか」を確認しましょう。
③ 見積りと説明が明確で丁寧か
良い専門家ほど、「なぜこの費用がかかるのか」「どこまでの範囲が対象になるのか」などを明確に説明してくれます。見積りが不明瞭、内容が曖昧な場合は注意が必要です。
④ 他士業と連携しているか
境界問題では測量だけでなく、登記・評価・調停・訴訟など他の専門家との連携が必要になる場合があります。不動産鑑定士や弁護士、司法書士と連携している専門家なら、ワンストップで対応してもらえることもあります。
⑤ トラブル対応の姿勢と実績
「境界トラブルに発展した際の対応経験があるか」「相手方との立会いの進め方をどう考えているか」など、万が一の場面を想定した質問をしてみましょう。冷静かつ柔軟な対応力の有無が問われます。
⑥ 資格と登録の有無を確認
当然ながら、**土地家屋調査士は国家資格であり、各地の土地家屋調査士会に登録されています。**測量士も国土交通省の登録名簿で確認できます。資格者証の提示をお願いしても問題ありません。
専門家選びでよくある失敗と注意点
▸ 安さだけで選ぶと後悔する
「費用が安い」だけを理由に依頼してしまうと、測量の精度が低かったり、後のトラブルに対応してくれなかったりすることがあります。測量は“精密な専門業務”です。価格よりも「品質」と「対応力」を重視すべきです。
▸ 対応が遅い・連絡がつきにくい
境界の確認や立会いには、隣地所有者との調整やタイミングが重要です。レスポンスが遅い専門家では、売却や再建築のスケジュールに影響することも。最初のやりとりから、連絡の丁寧さやスピード感を見極めましょう。
▸ 測量図や書類の取り扱いが雑
測量図や境界確認書は将来のトラブルを防ぐ「証拠資料」になります。誤記や保存方法の不備がないか、確認を怠らないようにしましょう。
相談時に確認すべき質問例
初回相談時に以下のような質問をしてみると、専門家の対応力や考え方を見極めやすくなります。
- この地域での測量実績はどのくらいありますか?
- 相手方が立会いに応じてくれない場合はどう対応しますか?
- 見積りにはどこまでの業務が含まれていますか?
- 測量図や境界確認書の保管方法についてアドバイスはありますか?
専門家の説明に納得できるかどうかは、信頼関係を築くうえで非常に大切なポイントです。
「話しやすい人」を選ぶことも重要
技術的な専門性も重要ですが、「この人なら信頼して任せられる」「きちんと話を聞いてくれる」という安心感も、実は非常に大切です。境界問題は人間関係の調整が必要な場面も多く、専門家の“対人スキル”も問われます。
まとめ:測量士選びが売却成功の第一歩
不動産売却や相続をスムーズに進めるには、最初の一歩である“測量”を信頼できる専門家に任せることが重要です。その選択が、トラブルの有無や売却価格、手続きのスピードに大きく影響します。
安さや広告のうまさに惑わされず、「実績・信頼・対応力」を見極めて、納得のいく専門家を選びましょう。
まとめ:測量で不動産売却を有利に進めるために
ここまで、不動産売却における測量の重要性、必要となるケース、手続きの流れ、費用、トラブル事例、そして専門家の選び方まで幅広くご紹介してきました。最後に、これらの情報をもとに「なぜ測量が不動産売却に不可欠なのか」「測量を通じてどのように有利に売却を進められるのか」を整理してまとめます。
測量は「価格」と「安全性」の根拠を与える
不動産の売却において、買主が最も重視するのは、「この土地に法的な問題がないか」「面積は正確か」「境界は明確か」といった点です。これらの疑問に明確な根拠を与えるのが**「測量図」「境界確認書」**といった正式な書類です。
特に確定測量がされていない土地では、「境界が曖昧=トラブルのリスクがある」と見なされ、売却価格が大きく下がる要因になります。一方、しっかりとした測量を行って境界を明確にしておけば、買主にとっての安心材料となり、価格交渉や売却後のトラブルを回避しやすくなります。
測量が後回しにされる理由とリスク
実際には、「売却する前に測量をしておこう」と考える方はそれほど多くありません。費用や手間がかかるため、つい後回しにされてしまうのが実情です。しかし、以下のようなケースでは、測量を行わなかったことが後々の大きな問題につながることもあります。
- 売買契約後に境界紛争が発覚し、契約解除や損害賠償につながる
- 隣地との境界交渉がこじれ、売却そのものが長期化・中断する
- 買主が住宅ローンを使えず、取引が成立しない
- 実測面積が登記と異なり、予定していた価格で売れない
測量は単なる「確認作業」ではなく、安全な売却を保証するための前提条件だという意識が必要です。
測量で“有利な条件”を引き出す方法
確定測量を行うことで、不動産の「品質」が可視化されます。これは中古住宅における“インスペクション(建物診断)”と同じで、買主にとってリスクが少なく信頼できる物件という印象を与えます。
また、確定測量が完了していれば、「即引渡し可能」「融資審査が通りやすい」「後々のトラブルが起きない」という条件が揃うため、売却活動をより有利に進めやすくなります。
価格交渉時も「確定測量済・境界明示済み」の物件とそうでない物件では、買主側のスタンスが大きく変わります。売主としては、こうした点を武器に強気で価格設定を行うことが可能になります。
測量は“資産の棚卸し”にもつながる
相続や不動産の整理を考える上でも、測量は重要な役割を果たします。特に地方の土地や古くからの相続物件では、「登記簿の面積と実際が違う」「境界が不明」「相続人同士で分けられない」といった問題が多く見受けられます。
こうしたケースでは、測量を通じて資産の全体像を明らかにし、適正な分割や評価を行うことが可能となります。結果として、売却の準備が整い、スムーズに資産整理を進めることができるようになります。
測量と不動産鑑定の連携がもたらす価値
さらに、測量の結果をもとに不動産鑑定士による評価を行えば、価格の裏付けが取れた売却活動が可能になります。特に相続税対策や、取得価格が不明な土地の譲渡所得税申告の際などに、鑑定評価の有効性が高まります。
不動産の評価に精通した専門家と、境界や法的状況を正確に把握する測量士が連携することで、「適正価格+リスクなし」の安心・納得できる売却が実現します。
測量を活かすには、専門家との早期相談がカギ
測量を実施するには、隣地所有者との日程調整、役所での資料取得、現地調査、測量図作成など、少なくとも数週間〜数カ月の期間が必要です。売却を検討し始めた段階で、「まずは専門家に相談する」ことが結果的に大きな差を生みます。
また、境界問題や測量の必要性について判断がつかない場合でも、土地家屋調査士や不動産鑑定士に状況を見てもらうことで、適切な判断ができるようになります。
まとめ:測量は「備えあれば憂いなし」
測量は、売却前の「コスト」ではなく、安心・納得できる売却を実現するための「投資」と捉えるべきです。測量を通じて不動産の価値が明確になり、トラブルの芽を早期に摘むことができるからこそ、結果として高く・早く・安全に売却できる確率が上がるのです。
不動産売却の第一歩として、ぜひ信頼できる測量士や不動産鑑定士にご相談ください。プロの知見を活かし、大切な資産を最大限に活かす売却戦略を立てましょう。
測量は「地味で面倒な手続き」と思われがちですが、不動産売却を成功させるうえで非常に重要なステップです。特に、土地の売却では、正確な面積と明確な境界が買主の信頼を得る鍵となります。
トラブルを未然に防ぎ、安心・納得の売却を実現するためには、早めに測量を検討し、専門家と連携して準備を進めることが大切です。 もし、「測量が必要なのかよくわからない」「隣地との境界が曖昧かもしれない」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
経験豊富な不動産鑑定士や測量士が、あなたの売却を全力でサポートいたします。