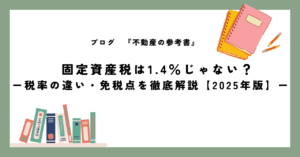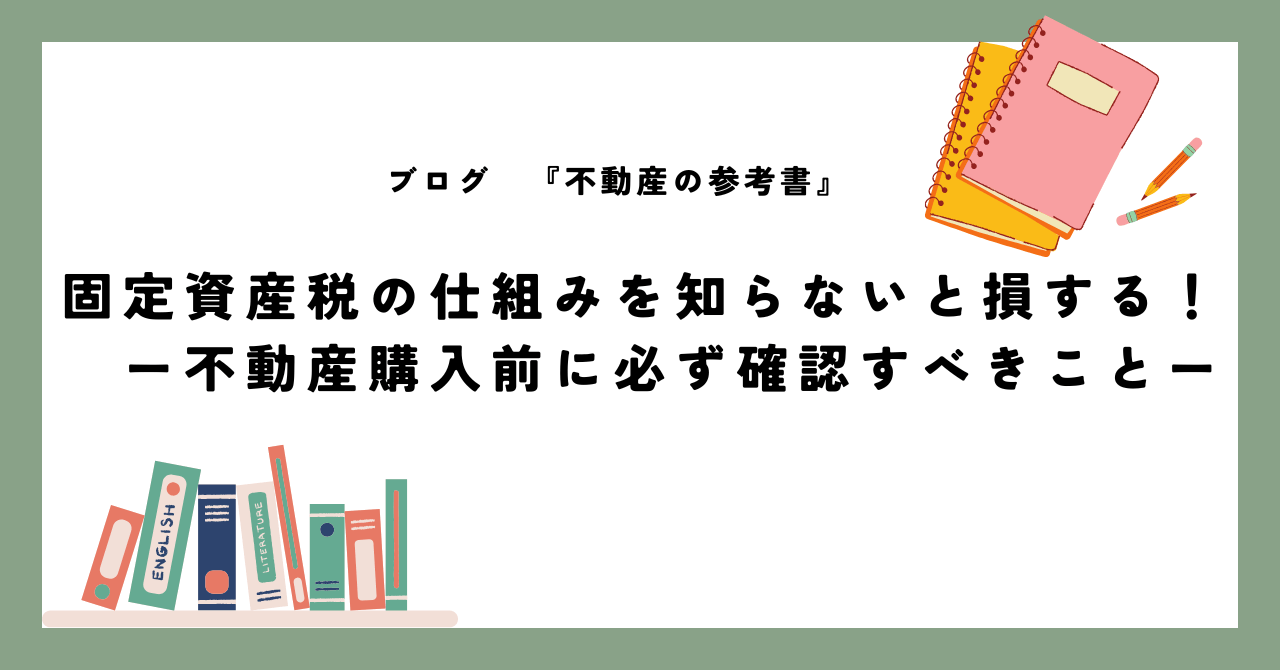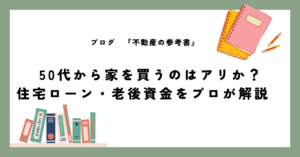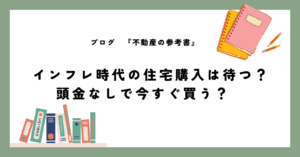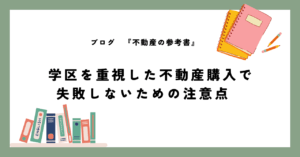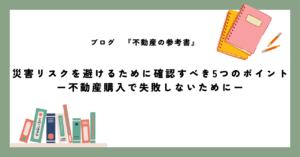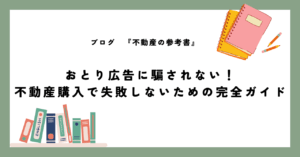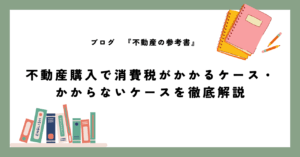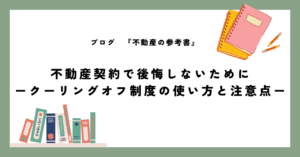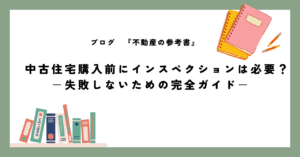なぜ固定資産税を理解しないと損するのか
不動産を購入すると、契約時の諸費用や住宅ローンの返済だけでなく、毎年必ず発生する税金があります。その代表が「固定資産税」です。これは土地や建物を所有している限り継続的に課される税金で、購入後のランニングコストとして無視できません。
固定資産税の仕組みを理解せずに購入すると、資金計画が大きく変わってくるリスクがあります。例えば、地域や土地の大きさなどによって税額は異なってきますので、一概には言えませんが、年間数万円から数十万円の負担が発生する場合があります。
住宅ローンの返済に加えてこの税金を支払うことになるため、家計に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、固定資産税は購入した翌年から課税され、納付書が毎年送付されます。支払いは年4回の分割が一般的ですが、地域によっては都市計画税が加わる場合もあり、負担額はさらに増えることがあります。こうした仕組みを知らないまま購入すると、「こんなにかかるとは思わなかった」という事態になりかねません。
不動産購入前に固定資産税の概算を把握し、資金計画に組み込むことが重要です。評価額や軽減措置を確認し、余裕を持った計画を立てることで、購入後の生活を安定させることができます。
本ブログでは、この固定資産税の仕組みを解説していきます。不動産購入で、後からこんな筈ではなかった、というような状況を避けるためにも、最後までお読みになり、固定資産税の理解を深めていただけましたら幸いです。

このブログを読んで分かること
- 固定資産税の基本的な仕組み
- 課税対象と納税義務者のルール
- 評価額の決まり方と税率
- 都市計画税との違いと負担額
- 納付方法・支払い時期の詳細
- 軽減措置や節税のポイント
固定資産税とは?基本の仕組みを簡単に解説
ここから本題に入ります。
まずは、固定資産税の基本とその仕組みを解説していきます。
固定資産税の概要
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人に課される地方税で、毎年必ず発生する税金です。購入時の諸費用や住宅ローンに目が行きがちですが、固定資産税は購入後のランニングコストとして長期的に家計に影響します。そのため、資金計画に組み込むことが非常に重要です。
課税対象は主に土地と家屋ですが、より厳密には事業用の機械や設備などの「償却資産」にも課税されます。ただし、本ブログでは不動産購入者向けの内容に絞るため、償却資産については割愛します。
課税対象と納税義務者
固定資産税の課税対象は、主に土地と家屋です。土地には宅地や農地、建物には住宅や店舗などが含まれます。これらを所有している限り、毎年固定資産税が課されます。
納税義務者は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人です。この基準日が非常に重要で、年の途中で売却しても、その年の税金は原則として1月1日時点の所有者が負担します。例えば、3月に物件を売却した場合でも、その年の固定資産税は売主が納めることになります。
ただし、売買契約時には「日割り精算」を行うのが一般的です。これは、引渡し日以降の期間に相当する税額を買主が負担する仕組みで、契約書に明記されます。精算方法や負担割合は取引ごとに異なるため、契約時に必ず確認しましょう。
この売買による清算については、後程、詳しく説明します。
このように、課税対象と納税義務者のルールを理解しておくことで、購入後の税負担を正しく予測し、トラブルを防ぐことができます。
課税標準額と評価額の仕組み
固定資産税の計算は、市町村が算定する固定資産評価額を基準に行われます。
この固定資産税評価額は市場価格とは異なり、固定資産税評価基準に基づいて決定されます。評価額が高いほど税額も増えるため、購入前に概算を把握しておくことが大切です。
土地の固定資産税評価額についていうと、地価公示価格の70%程度の水準になっています。
税率と都市計画税
固定資産税の標準税率は、1.4%とされており、1.4%であることが多いです。
ですが、標準税率なので、1.4%でない市町村もあります。なお、制限税率として2.1%が定められていますので、これよりも高いことはありません。
各市町村のホームページや固定資産税課に確認してもらえれば分かります。
さらに、固定資産税とセットで考えてもらいたいものに、都市計画税があります。
名前のとおり、都市計画区域内でのみ課税されます。言い方を代えれば、都市計画区域外では課税されない、ということになります。
この都市計画税の税率は、0.3%であることが多いです。この0.3%は制限税率でもあり、0.3%以下の市町村もあります。
参考までに、税額の目安をお示ししますと、固定資産税評価額が2,000万円で、小規模住宅用地の特例が適用されれば、固定資産税は年間約5万円、都市計画税を含めると約7万円になります。
小規模住宅用地の特例は、この後、説明致します。
納付方法とタイミング
固定資産税は、不動産を購入した翌年から課税されます。
納付書は毎年4月から6月頃に市町村から送付され、税額や支払い方法が記載されています。
支払い方法は年4回の分割払いが一般的で、納付書には各期の支払期限が明記されています。一括払いも可能ですが、期日を過ぎると延滞金が発生するため注意が必要です。延滞が続くと督促状や差押えなどの厳しい措置が取られる場合もあるため、計画的な管理が不可欠です。
固定資産税は毎年必ず発生するため、納付スケジュールを把握し、住宅ローンや生活費と合わせて資金計画に組み込むことが重要です。特に、都市計画税が加わる場合は負担額が増えるため、事前に確認しておくと安心です。
評価替え
固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。
地価の変動や建物の老朽化などを反映するため、税額が増減する可能性があります。
これに関して、もう少し詳しく説明しますと、土地価格が上昇している場合には、3年ごとの評価替えによって、反映されることになります。
一方で、土地価格が下落している場合には、毎年時点修正を行い、下落を反映させることになっています。
上昇は3年に1度、下落は毎年となっています。これは納税者には嬉しいですね。
評価額が高すぎる場合の対処法
評価額が不当に高いと感じた場合は、不服申立が可能です。申し立て先は「固定資産評価審査委員会」で、毎年4月1日から納税通知書の交付後一定期間内に申請できます。
書面での手続きとなりますので、不当であると考える理由(主張又は計算根拠等)を記載する必要があります。
主張又は計算根拠等を立証する資料がある場合には、その資料も提出することが出来ます。
東京都の詳細は、こちらをご参照下さい。
評価額を確認する方法
評価額は、毎年送付される納税通知書に記載されています。
納税通知書は、所有者に送付されますので、売買関係資料に、通常含まれています。
万一、無かった場合には、仲介会社か売主に問合せましょう。
なお、賃借人などの、その不動産の利害関係人は、利害関係を証明する資料をもって、市町村の固定資産税課に行くと、評価証明書を入手することが出来ます。
ですが、利害関係人ですので、買主というだけでは、評価証明書を入手することは出来ませんので、注意して下さい。

軽減措置
固定資産税には、負担を軽減できる制度があります。
代表的なのが新築住宅の軽減措置で、条件を満たせば3年間税額が半額になります。さらに、小規模住宅用地の特例では、200㎡以下の土地の評価額が6分の1に軽減されます。これにより、都市部の戸建てやマンション敷地では大幅な軽減がされています。
小規模住宅用地の特例は、都市計画税にも適用されますが、軽減は1/3となっています。
この軽減措置は、基本的には、課税側の方で、適用しますので、届け出などは不要です。
ですが、土地や家屋の状態に変化があった場合には、その変化が反映されていない場合がありますので、確認をした方がいいでしょう。
レアケースになりますが、課税側のミスということもありますので、購入前に、一度確認することをおすすめします。
この章のまとめ
固定資産税は、不動産購入後に必ず発生する税金です。仕組みを理解し、評価額や軽減措置を確認しておくことで、購入後の家計を安定させることができます。
固定資産税はいくらかかる?計算方法と目安
固定資産税の基本的な仕組みを理解したところで、実際の計算方法を見ていきましょう。
計算というと、拒絶反応を起こす方もおられるかもしれませんが、難しい計算ではありませんので、ぜひ読み進めて下さい。
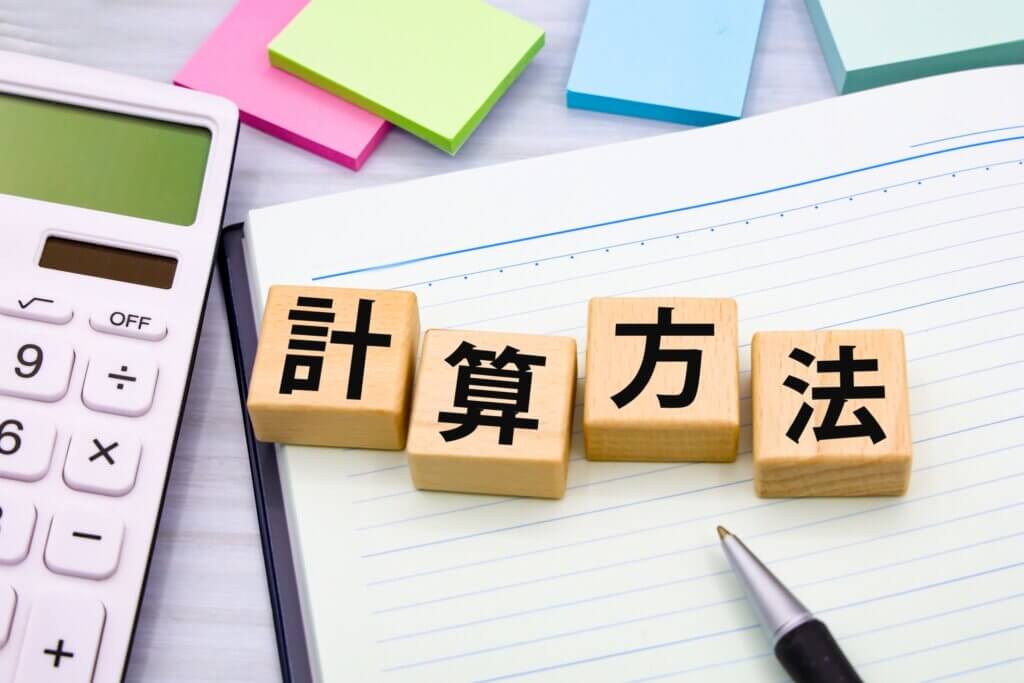
固定資産税の基本計算式
固定資産税の金額は、次の計算式で求められます。
税率は、標準税率の1.4%とします。先に説明させていただきましたが、この税率は市町村によって異なりますので、必ず確認して下さい。
固定資産税額 = 固定資産評価額 × 負担調整×1.4%
評価額は、市町村が算定する固定資産評価額であり、市場価格とは異なります。評価額が高ければ税額も増えるため、購入前に概算を把握しておくことが重要です。
気になるのは、負担調整でしょうか。
難しく思われたかもしれませんが、先に説明させていただいた小規模住宅用地の特例は、この負担調整になります。
参考に、これを数式にしますと、以下のとおりとなります。
固定資産税額 = 固定資産評価額 × 1/6×1.4%
こうしてみると、小規模住宅用地の特例により、固定資産税額が、ずいぶんと減額されていることが分かるかと思います。
なお、固定資産税評価額に負担調整を行ったものを、課税標準額といいます。
商業地の場合には、この負担調整は、少し難しくなりますが、計算自体は、課税主体の方で行いますので、無理に理解をしなくても大丈夫でしょう。
先にも説明させていただいたとおり、計算そのものよりも、適用条件を理解される方が重要です。
都市計画税を含めた総額の目安
固定資産税に加えて、都市計画区域内の土地や建物には都市計画税(最大0.3%)が課されます。
例えば、評価額が2,000万円で、小規模住宅用地の特例が適用される場合には、以下のとおりとなります。
- 固定資産税:2,000万円 × 1/6 × 1.4% ≒ 5万円
- 都市計画税:2,000万円 × 1/3 × 0.3% ≒ 2万円
合計で年間約7万円の税負担となります。これが毎年発生するため、住宅ローンと合わせて考えると負担は決して小さくありません。
評価額による税額のシミュレーション
評価額によって税額は大きく変わります。以下は目安です。前提は同様で、小規模住宅用地の特例が適用されるとします。
- 評価額1,000万円 → 固定資産税約2万円(1,000万円 ✕ 1/6 ✕ 1.4%)
- 評価額3,000万円 → 固定資産税約7万円(3,000万円 ✕ 1/6 ✕ 1.4%)
都市計画税を含めるとさらに数万円上乗せされます。購入前に評価額を確認し、資金計画に組み込むことが不可欠です。
注意すべきポイント
- 評価額は3年ごとに見直されるため、税額が変動する可能性があります。
- 新築住宅には軽減措置があり、条件を満たせば3年間半額になります。
- 小規模住宅用地の特例(200㎡以下の土地は評価額が6分の1)も活用できます。
この章のまとめ
固定資産税は、不動産購入後に毎年発生する重要なコストです。評価額や都市計画税を含めた総額を事前に把握し、資金計画に組み込むことで、購入後の家計を安定させることができます。
固定資産税はいつから発生する?支払い時期と注意点
課税タイミングは購入翌年から
固定資産税は、不動産を購入した年には原則課税されません。課税が始まるのは翌年の1月1日時点で所有している人です。つまり、年末に購入した場合でも、翌年から税金が発生します。この仕組みを理解していないと、思わぬ出費に驚くことになります。
納付書の送付時期
毎年4月から6月頃に、市町村から納付書が送付されます。納付書には年間の税額と支払い方法が記載されており、忘れずに確認することが重要です。納付書が届かない場合は、役所に問い合わせましょう。
支払い方法と回数
固定資産税の支払いは、年4回の分割払いが一般的です。納付書には4期分の支払期限が記載されており、期日までに納付しないと延滞金が発生します。一括払いも可能ですが、家計管理の観点から分割払いを選ぶ人が多いです。
購入年の「日割り精算」に注意
購入した年は、固定資産税の納税義務者が1月1日時点の所有者であるため、売主が税金を納めます。しかし、売買契約時に日割り精算を行うケースが一般的です。これは、引渡し日以降の期間に相当する税額を買主が負担する仕組みです。契約書に記載されるため、確認を怠らないようにしましょう。
支払いを忘れた場合のリスク
支払いを怠ると、延滞金が加算されるだけでなく、最悪の場合は差押えの対象になることもあります。固定資産税は地方税であり、滞納に対しては厳しい措置が取られるため、計画的な納付が不可欠です。
この章まとめ
固定資産税は購入翌年から課税され、納付書は春に届きます。支払いは年4回の分割が基本ですが、購入年には日割り精算がある点も押さえておきましょう。こうした仕組みを理解し、資金計画に組み込むことで、購入後の家計を安定させることができます。
固定資産税を節約する方法
新築住宅の軽減措置を活用
新築住宅には、固定資産税の軽減措置があります。条件を満たせば、3年間は税額が半額になります。
- 対象:居住用の新築住宅
- 条件:床面積が50㎡以上280㎡以下など
この制度を知らないと、数十万円の節約機会を逃すことになります。購入前に条件を確認し、適用を受けるための手続きを忘れないようにしましょう。
小規模住宅用地の特例
土地に関しては、小規模住宅用地の特例が適用されます。
- 対象:200㎡以下の住宅用地
- 内容:評価額が6分の1に軽減
例えば、評価額が600万円の土地なら、課税対象額は100万円に減り、税額も大幅に下がります。都市部の戸建てやマンション敷地では、この特例が適用されるケースが多いため、必ず確認しましょう。
評価額の見直し申請
固定資産税は、市町村が算定する評価額を基準に課税されますが、誤りがある場合は見直し申請が可能です。
- 申請先:固定資産評価審査委員会
- 申請期間:納税通知書交付後、一定期間内
評価額が不当に高い場合、近隣の評価額や市場価格を根拠に申し立てることで、税額を減らせる可能性があります。
その他の節税ポイント
- 耐震改修や省エネ改修による減税:条件を満たせば固定資産税が一定期間減額
- 長期的な資産計画:評価替えのタイミング(3年ごと)を把握し、資産価値の変動に備える
この章のまとめ
固定資産税は毎年発生するため、軽減措置や特例を活用することで、長期的に大きな節約が可能です。新築住宅の軽減措置や小規模住宅用地の特例は特に効果が大きく、評価額の見直し申請も忘れずに検討しましょう。購入前に制度を理解し、適用条件を確認することが、賢い不動産購入の第一歩です。
不動産購入前に確認すべきこと
固定資産税の概算を把握する
不動産購入前に必ず確認したいのが、固定資産税の概算です。評価額によって税額は大きく変わるため、購入予定の物件がどの程度の負担になるかを事前に知っておくことが重要です。市町村の固定資産税課や不動産会社に問い合わせれば、概算を教えてもらえる場合があります。
評価額と課税対象を確認
固定資産税は土地と建物に課税されます。評価額は市町村が算定するため、購入前に「固定資産評価額」を確認しておくと安心です。評価額が高い物件は税負担も大きくなるため、資金計画に反映させることが不可欠です。
都市計画税やその他の税金も考慮
固定資産税だけでなく、都市計画税(最大0.3%)や不動産取得税など、購入後に発生する税金は複数あります。これらを含めた総額を把握し、住宅ローン返済と合わせてシミュレーションすることで、家計への影響を予測できます。
軽減措置や特例の適用条件を確認
新築住宅の軽減措置(3年間半額)や小規模住宅用地の特例(200㎡以下の土地は評価額が6分の1)など、節税につながる制度があります。購入前に条件を確認し、適用できるかどうかを不動産会社や役所に相談しましょう。
購入年の税負担と精算方法
購入年は原則として売主が固定資産税を納めますが、契約時に日割り精算を行うケースが一般的です。契約書に記載されるため、精算方法を確認し、引渡し後の負担額を把握しておくことが大切です。
この章のまとめ
不動産購入は物件価格や住宅ローンだけでなく、購入後の税負担も考慮する必要があります。固定資産税の概算、評価額、都市計画税、軽減措置などを事前に確認し、資金計画に組み込むことで、購入後の生活を安定させることができます。
まとめ:固定資産税を理解して賢く不動産購入を
固定資産税は「購入後のランニングコスト」
不動産購入時は物件価格や住宅ローンに目が行きがちですが、固定資産税は毎年必ず発生する税金です。評価額や都市計画税を含めると、年間数万円から数十万円の負担になることもあります。これを知らずに購入すると、家計に大きな影響を与えかねません。
購入前に確認すべきポイント
- 固定資産税の概算を把握し、資金計画に組み込む
- 評価額や都市計画税の有無を確認
- 軽減措置や特例(新築住宅の半額、200㎡以下の土地の評価額6分の1)を活用できるかチェック
賢く節税する工夫
新築住宅の軽減措置や小規模住宅用地の特例を利用すれば、長期的に大きな節約が可能です。また、評価額が不当に高い場合は不服申立を検討しましょう。こうした制度を理解し、適切に対応することで、税負担を最小限に抑えられます。
失敗しないための第一歩
固定資産税は「知らなかった」では済まない税金です。購入前にしっかり確認し、資金計画に反映させることが、安心して不動産を所有するための第一歩です。税金の仕組みを理解し、賢く制度を活用することで、購入後の生活を安定させましょう。