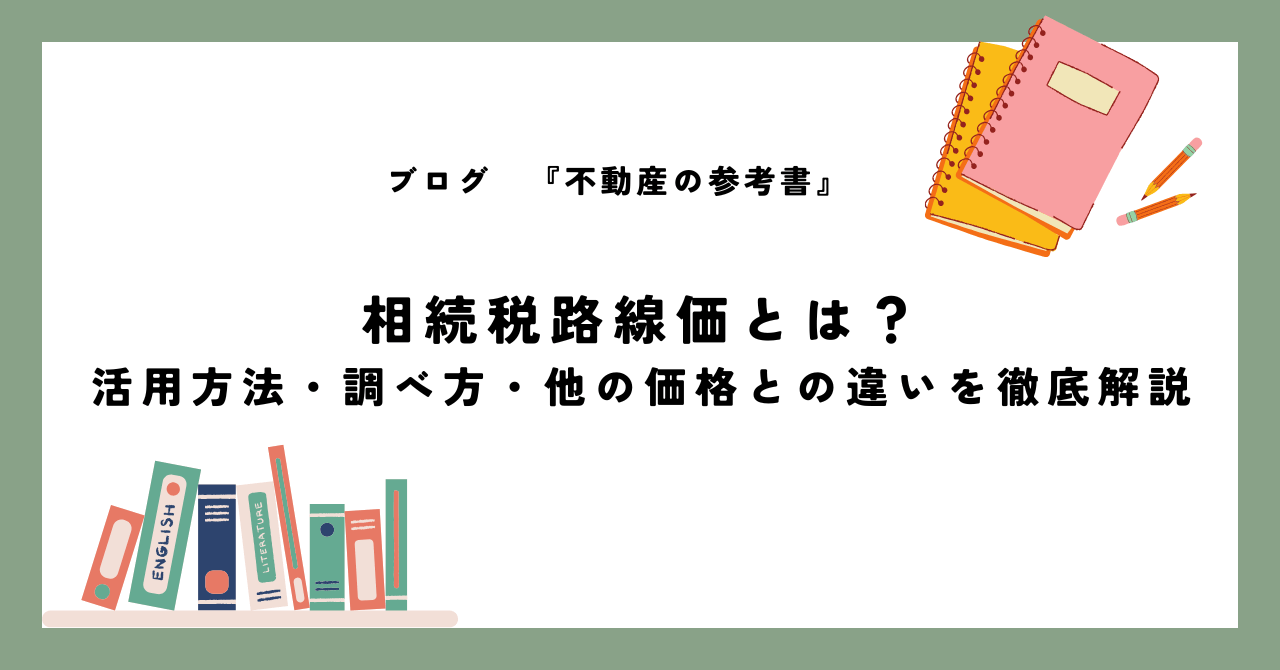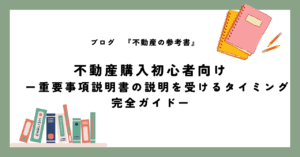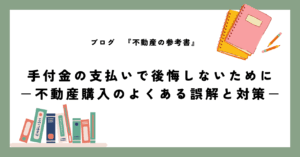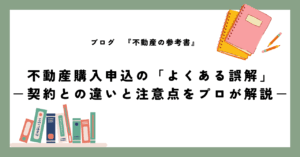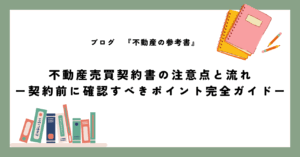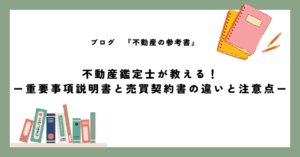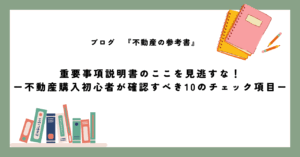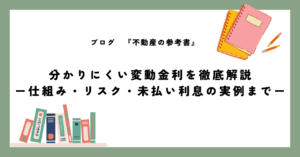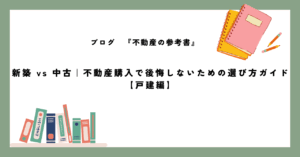相続税路線価は、ご存じでしょうか。
相続税路線価とは、国税庁が毎年発表する、土地1㎡あたりの価格情報であり、相続税や贈与税を計算する際に用いられる公的な評価基準です。
前記のとおり、相続税や贈与税の計算の際に用いられるものです。
そうしますと、不動産の相続や贈与がなければ、あまり関係がないと思われる方も多いかもしれません。
もちろん、直接的には、相続税、贈与税の計算の際に使用するものですが、相続税路線価はもっと活用できる場面があります。言い方を代えれば、他にもっと活用できる場面がありますので、利用しないのは、もったいないです。
そこで、本ブログでは、相続、贈与以外の目的で、相続税路線価を活用する方法について解説していきます。
「相続する土地の評価方法がわからない」「税理士や専門家に依頼する前に、基本だけでも押さえておきたい」──そんな方にとって、実務にも役立つ情報をまとめています。ぜひ最後までお読みください。
なお、特に注記のない限り、以下、路線価とありましたら、相続税路線価のことになります。(固定資産税にも路線価があるためです。)
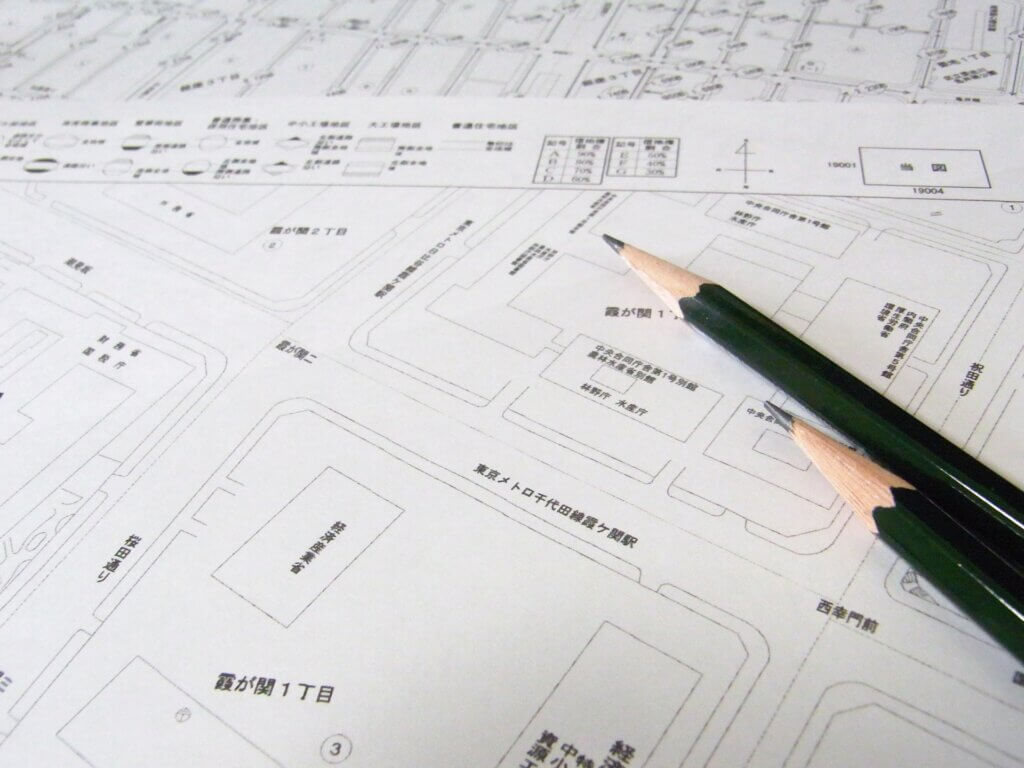
1.活用方法
いきなりですが、路線価の活用方法です。2つあります。
- 土地価格を知ることができる
- 借地権割合を知ることができる
特に、1番目の土地価格を知ることができる、は路線価の最もおすすめ活用方法です。
土地価格を知りたいと思っても、一般の方には、難しいかもしれません。しかし、路線価を活用することによって、簡単に、土地価格を知ることができる場合があります。
2. 相続税路線価とは?
活用方法を説明する前に、路線価の基本知識が必要となりますので、ここで、相続税路線価について、まず説明させて下さい。
先に触れておりますが、路線価は、相続税、贈与税の計算の基礎となるものですが、これから説明する活用方法においては、あまり関係のないことになりますので、以下本ブログでは、活用と関係のないことは、説明を割愛させていただきます。
ポイントは、以下の6つです。
路線ごとに価格が設定してある
路線価は、特定の道路(路線)ごとに1㎡あたりの価格が細かく設定されています。この価格設定により、土地の評価がより正確かつ公平に行われる仕組みとなっています。たとえば、同じエリア内でも、道路の幅員や周辺環境、商業施設の有無などによって路線価が異なる場合があります。これにより、市街地の宅地については、どの道路に面しているかによって土地の評価額が異なることになります。また、毎年国税庁が発表するため、最新の市況を反映した価格となる点も特徴です。
調べたい土地が接する道路の路線価から、土地の価格が分かりますので、とても便利です。
1㎡当たりの価格である
先のとおり、路線価は、各道路に付設してありますが、この付設してある価格は、1平方メートル(㎡)あたりの価格(単価)になります。
調べたい土地が複数あって、その比較をしたい場合には、単価のままでいいかもしれませんが、土地の総額を知りたい場合には、1平方メートルあたりの価格に、お調べしている土地の面積を乗じる必要があります。
慣習的に、土地の単価、面積を坪(つぼ)で表記することも、まだ多いように思われますが、路線価は、1㎡当たりの価格ですので、ご注意下さい。
参考までに、坪単価に換算するには、1㎡当たりの価格(単価)を0.3025で割り戻せばいいです。
路線価が300とありましたら、300,000円/㎡ということになります。
300,000円/㎡÷0.0325≒992,000円/坪となります。
地価公示価格の80%となるように設定されている
相続税路線価は、公的な土地の価格指標としても知られていますが、その特徴の一つに「地価公示価格の80%程度に設定されている」という点があります。
従いまして、路線価そのものは、相続税や贈与税の計算のために用いられるものですので、取引ベースの価格にはなっていない、ということには、注意をして下さい。
後程、詳しく説明しますが、公示価格の80%水準ということは、路線価を80%で割り戻すことによって、公示価格水準になります。
路線価が300とありましたら、下記の計算をすることによって、地価公示価格ベースの価格となります。
300,000円/㎡÷0.8=375,000円/㎡となります。
これは、覚えておいて下さい。
標準的な土地の価格である
路線価は、路線に接する土地の価格になります。これは説明させていただいたとおりです。
ですが、その路線に接する土地には様々な土地があります。この様々な土地の価格を一つの路線価だけで、示すことは困難です。
ですので、路線価は、その路線に接する標準的な土地の価格を表している、ということを知っておいて下さい。
標準的な土地というのは、整形地で、角地などではない、ということになります。極端に規模が大きい場合、大きな高低差があるような場合には、路線価から直接価格を知ることは困難になるかもしれません。
なお、地域によりますが、規模が大きいことは必ずしも減価にはなりません。マンション用地となるような大規模地でしたら、むしろ、高値となる可能性もあります。
1月1日時点の価格である
路線価は毎年発表されていますが、1月1日時点の価格を示しています。これは、地価公示と同様です。
毎年7月初めに公表される
路線価は、毎年、7月初めに公表されます。インターネットで閲覧可能です。公表されてすぐは、恐らくですが、金融機関の方などが多用されるのか、つながりづらいことがあります。
3月下旬に発表される地価公示価格と比較すると、少し遅くなっています。
地価公示は、不動産鑑定の評価結果(鑑定評価書)を公表すればいいのですが、路線価は、各路線に路線価を付設しなければいけないので、手間を要しますので、仕方のないところです。
3. 路線価の調べ方
相続税路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から無料で確認することができます。インターネットで「国税庁 路線価」と検索すれば、すぐに該当ページにアクセス可能です。
地図からでも、地名からでも検索できます。
次に、路線価図で該当する道路に記載された価格(単価)を見つけます。例えば、「450D」と書かれていれば、1平方メートルあたり45万円という意味になります。
なお、場所によっては、路線価のない地域があります。
このような地域では、「倍率方式」が適用されます。この場合、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。
4. 他の価格との関係
土地の評価においては、相続税路線価の他にも、いくつかの公的価格や民間の実勢価格が存在します。
● 公示価格との関係
公示価格とは、国土交通省が発表する標準地における正常な価格であり、土地取引の指標となる価格です。路線価はこの公示価格の概ね80%程度を目安に設定されています。
● 固定資産税評価額との違い
固定資産税評価額は、市町村が固定資産税を課税するために算定するもので、通常は公示価格の70%程度とされています。したがって、評価額の高さは「実勢価格>公示価格>路線価>固定資産税評価額」という順になります。
● 実勢価格との違い
実勢価格とは、実際の取引で成立した価格のことで、地価のリアルな動向を反映します。路線価はこれより低く設定されるため、税務上の評価では節税効果が期待されることもあります。
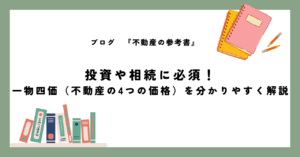
5. 借地権割合とその活用
借地権割合
路線価図には、借地権割合も併せて記載されています。これは、土地の価格評価を行う際に非常に重要な指標となります。多くの場合、路線価の数字の後ろにはA、B、Cなどのアルファベットが表示されており、これがそれぞれ異なる借地権割合を示しています。たとえば、Aが付いていれば90%、Bなら80%、Cであれば70%というように決められています。つまり、該当する土地の路線価に対応した借地権割合を掛けることで、借地権の評価額が計算できるのです。
具体的には、ある土地の路線価が10万円、借地権割合がB(80%)であれば、借地権の評価額は10万円×80%=8万円となります。このように、借地権の価格は一見難しそうに感じますが、路線価図を参照することで、比較的簡単におおよその評価額を把握することができます。
借地権割合は、土地の用途や地域、標準的な契約条件などを加味して決められており、全国一律ではなく、地価や周辺の建物状況にも大きく左右されます。都市部ではビルなど堅固な建物が多く、借地権割合も高めに設定されていることが一般的ですが、郊外や用途制限のある土地では割合が低くなる場合も少なくありません。
注意点
なお、借地権割合で注意していただきたいのは、これも土地の場合と同様に、標準的な借地権になるということです。
借地権には、堅固建物所有目的、非堅固建物所有目的といった契約目的の違い、残存契約期間、契約内容に利用上の制約がないか、などで、借地権の価格も変わってくることです。
例えばですが、借地権割合が80%であったとしましょう。
周辺は、中高層のビル(堅固建物)が多く建ち並んでいる中で、お調べの土地は木造建物(非堅固)だったとします。この場合、借地権割合の80%に相当するのはビルが建っている借地権になります。
そうしますと、木造の非堅固建物所有目的ですと、利用も制限されますので、ビルの借地権よりも安くなります。
通常は、堅固建物に条件変更するために必要となる条件変更承諾料を考慮したりします。
これについては、少し難しくなりますので、機会を改めて、説明したいと思います。
底地価格
また、借地権価格が分かるということは、その裏返しで、底地価格も分かるということになります。
同様に借地権割合が80%でしたら、残りの20%が底地価格の目安となります。
底地とは、他人がその土地に建物を建てる権利(借地権)を持っている土地、つまり借地権が設定されている土地の所有権部分を指します。一般的に、土地所有者は底地のみを所有し、借地権者はその土地を利用して建物などを所有・使用しています。底地の所有者(地主)は、土地そのものの所有権を持っているものの、その土地を自由に使ったり、建物を建てたりすることはできません。なぜなら、すでに借地権者がその土地を借りて使っているからです。
このため、底地は自用地(所有者が自由に利用できる土地)と比べて利用価値が制限されています。地主は地代を受け取ることができますが、土地そのものの利用や処分については借地契約の内容に大きく左右されます。たとえば、借地権者が契約を更新し続けるかぎり、地主はその土地を使えませんし、売却する場合も借地権付きの土地としての価値で評価されます。
底地の価値(底地価格)は、一般的にその土地の自用地評価額から借地権価格を差し引いた残りが目安となります。たとえば、借地権割合が80%であれば、残りの20%が底地価格となります。つまり、「底地価格 = 自用地評価額 ×(1-借地権割合)」という計算式で表されます。これは、土地全体の所有権のうち、地主が持つ部分が20%、借地権者が持つ部分が80%ということを意味しています。
また、底地価格は借地権の内容や契約期間、利用上の制約、地代の額、更新料や承諾料の有無など、さまざまな要因によって実際の取引価格が上下します。特に、借地権者と地主の関係や、借地契約の安定性、借地権者の信用力なども考慮されます。さらに、土地が将来的に更地に戻る可能性や、借地契約の終了・解除条件によっても底地の評価は変わってきます。
たとえば、底地を売却する場合、買主は借地権者に対する権利・義務を引き継ぐことになるため、通常の土地取引よりも交渉や調整が多くなります。多くの場合、底地と借地権をまとめて一体化し、その土地を完全に所有できる「完全所有権」にすることによって、はじめて本来の土地価値が発揮されます。そのため、底地と借地権者間での交渉や、双方の合意による一括売却や交換が行われるケースも少なくありません。
このように、借地権価格が分かるということは、その裏返しで底地価格も把握できることを意味します。たとえば、借地権割合が80%でしたら、残りの20%が底地価格の目安となるのです。
6. まとめ:相続税路線価をもっと活用しましょう
相続税路線価は、相続や贈与の場面で不動産の評価基準として広く用いられていますが、その名称から「相続や贈与の際にしか使えないもの」と考えてしまう方も少なくありません。しかし、実際には路線価は日常のさまざまな局面で役立つ、非常に有用な指標です。
例えば、土地の売買を考えている場合や、不動産を担保に資金調達を検討したい時などにも、この路線価を活用することで、土地や借地権、底地の価格のおおまかな目安を把握することができます。これは、相続や贈与だけでなく、資産運用や事業計画を立てる際にも大変有益です。また、不動産を複数所有している場合、それぞれの評価額を比較することで、より効率的な資産管理や将来的な分割の検討材料にもなります。
路線価を活用することで、相続や贈与時だけでなく、日常的な資産管理や将来に備えた準備にも役立てることができるのです。これにより、不動産の価値を適切に把握し、無用なトラブルや誤解を防ぐことにもつながります。
ぜひこの便利な指標である相続税路線価の特徴と使い方を理解していただき、幅広い場面で積極的にご活用いただければと考えています。