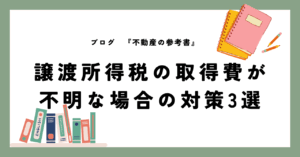3月19日に、令和7年地価公示価格が発表されました。
今年も、全国的に上昇という内容になっています。
土地価格が上がっている一方で、賃料はどうなっているのでしょうか。
少し理論的な話しになりますが、土地と賃料の間には、元本と果実の関係がありますので、土地価格が上昇すれば、賃料も上昇することになります。
更に、建築費も上昇していますので、地代、家賃ともに上昇している、と言えるでしょう。

そうしますと、物件を貸しているオーナーからしますと、地代、家賃の増額を、賃借人に申し入れたいところです。
相場としての賃料が上がっているのに、これを長期間放置しますと、相場の賃料と現在の賃料がかけ離れていきます。
この差が大きくなった時に、増額を申し入れても、増額幅があまりに大きいと、テナントは難色を示し勝ちです。
また、仮に増額出来たとしても、希望通りに上げられないかもしれません。
そうしますと、上げ幅が小さいうちに、小まめに増額していくことが一つのポイントになります。
今回は、賃料増額交渉について、説明をしていきます。

1.用意したい資料
交渉に当たり、資料があった方がいいです。
口頭で、賃料の増額を申し入れて、それを承諾してくれればいいですが、通常は、困難でしょう。
地代、賃料が上がっている根拠資料を示した方が、交渉もスムーズとなります。
では、この資料には、どのようなものがあるでしょうか。
(1)路線価図
(2)地価公示価格
(3)固定資産税・都市計画税納税通知書
(4)周辺事例を集めたもの
(5)不動産鑑定評価書
以下、それぞれ説明していきます。

(1)路線価図
正確にいうと相続税の路線価図になります。
国税庁のホームページから、見ることが出来ます。
正確にいうと、と最初に前置きを付しましたが、路線価には固定資産税の路線価もあるからです。
通常は、路線価というと、国税庁の相続税路線価図のことをいいます。
固定資産税の路線価も場合によっては、活用出来ることもありますので、後程、少し触れます。
①路線価図
では、路線価図を見ます。
下図は、弊社事務所前を含む路線価図になります。

路線価図は、1月1日時点の価格となります。
路線価左上に、R6とありますので、令和6年(2024年)1月1日の価格ということです。
1月1日時点の価格になりますが、路線価が発表されるのは、毎年、7月になります。
路線価の名称のとおり、路線(道路)に、価格が付けられています。
その道路に接する土地の価格ということになります。
1㎡当たりの価格で、路線価は千円㎡ですので、弊社事務所前の路線価2,040は、2,040,000円/㎡ということになります。

②路線価図の活用方法
路線価図は、国税庁のホームページでは、過去7年分の路線価をみることができます。
同様に、弊社事務所前の前年(令和5年)の路線価をみてみます。

1,890となっていますので、1,890,000円/㎡となります。
では、交渉の為の資料としてどうするのかですが、今年の路線価が2,040,000円/㎡で、昨年の路線価が1,890,000円/㎡でしたので、路線価の上昇率は、
2,040,000円/㎡÷1,890,000円/㎡≒1.079(+7.9%)
と求められます。
路線価が7.9%上昇したので、賃料も上げて欲しい、と交渉することになります。
③固定資産税の路線価図
固定資産税の路線価図についても、少し説明します。
固定資産税の路線価図も、場合によって活用出来る場合があります。
東京都では、東京都主税局のHPから閲覧可能です。
同じ場所の固定資産税の路線価図を、下記に掲載します。

よく見ていただきたいのですが、相続税路線価図では路線価がないところでも、固定資産税路線価図では路線価がある場所があります。
相続税の路線価図がない路線の場合に、固定資産税の路線価が参考になる場合があります。
ですが、一つ注意していただきたいのが、相続税路線価は、毎年公表されるのに対し、固定資産税の路線価は3年1度となります。
最新のものは、現時点では、令和6年度のものとなります。
地価が下がっている場合には、時点修正をする為の修正率が公表されますが、上昇している場合には、据え置きとなります。
地価が上昇している場合には、あまり活用できないかもしれません。
本ブログの目的は、賃料を上げることですので、固定資産税路線価の活用は難しいかもしれません。
(2)地価公示価格
初めに、令和7年地価公示価格の話しをしました。
地価公示価格も活用の仕方としては、路線価と同様になります。
国土交通省のHPから、調べたい場所の近くの公示価格を調べます。
国土交通省のHPは良く出来ており、近くの調べたい場所と参考になりそうな公示地がありましたら、その地点をクリックしてみましょう。
その地点の概要が表示されます。
更に、画面の下の方に行きますと、過去の価格推移も掲載されています。
ここから、令和6年の価格と令和7年の価格、そして変動率も表示されていますので、過去2年分の路線価をしらべなければいけない路線価より、使い勝手がいいかもしれません。
公示価格と路線価は、それぞれ一長一短です。
先のとおり、公示価格は、変動率を計算しなくて済みますが、参考になりそうな地点を探すのが、難しい場合があります。一方で、路線価は、前面道路の路線価を見ればいいだけですから、簡単です。
なお、地価公示価格も路線価と同様で、その価格は、1月1日時点のものとなります。
参考までに、地価公示価格と似たものに、基準地(地価調査)というものがあります。
これも、地価公示と同様に活用出来ますが、地価公示の価格時点が1月1日であるのに対し、基準地の価格時点は、7月1日ということに注意する必要があります。

(3)固定資産税・都市計画税納税通知書
先に2つ説明させていただきましたが、先の2つと比較すると、この固定資産税・都市計画税納税通知書を活用する方法が、より説得力があると思っています。
御存知のことと思われますが、固定資産税と都市計画税は、1月1日時点の所有者に課税されます。
地代であれば土地、家賃であれば事務所ビル、賃貸マンションになりますが、固定資産税・都市計画税は運用経費となります。
この運用経費が増加しているのだから、賃料を値上げして欲しい、というのは一定の説得力があるものと考えています。
また、通常、賃貸借契約書には、公租公課が増減した時には、賃料交渉が出来る、といったような内容が盛り込まれていることが多いですから、この点においても利に適っています。

(4)周辺事例を集めたもの
この方法も説得力があるという点では、活用を検討したい資料です。
この方法の最大の欠点は、先の3つの方法と比較すると、手間がかかるということです。
似ている事例を収集して、一覧表等にまとめるのには、少し手間がかかります。
また、地代の場合には、一般の方が、事例を集めるのは無理ではないかと推測します。
家賃の場合に、手間暇を惜しまない、ということでしたら、積極的に活用したい方法です。
なお、後程説明しますが、管理を不動産会社にお願いしている場合でしたら、その不動産会社に資料を作ってもらうのもいいかもしれません。
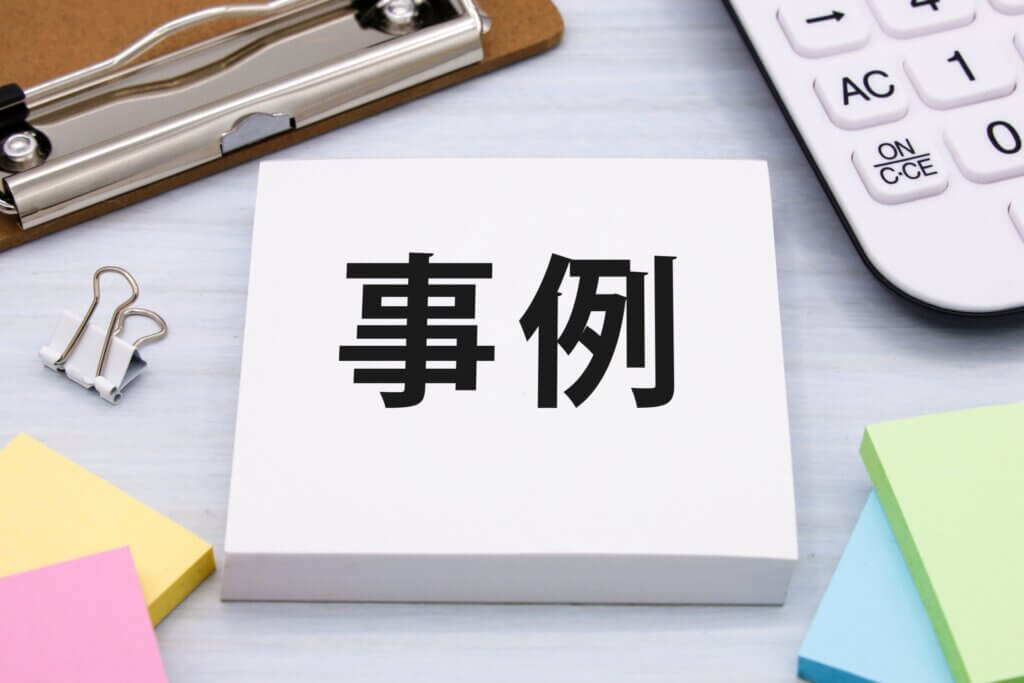
(5)不動産鑑定評価書
費用はかかってしまいますが、一番効果があるのは、不動産鑑定評価書を取得して、先方に提示することでしょう。
鑑定評価に当たり、必要な資料をお願いすることを除けば、手間は一切かからない、ということもメリットになります。
先のとおり、鑑定評価書の作成には、不動産鑑定士に鑑定料を支払う必要がありますが、費用を掛けてまで取得しているということで、先方に、賃料交渉の本気度を示すことが出来ます。
また、今後、調停手続きに至った場合でも、鑑定評価書を証拠書類として提示することにより、鑑定評価書の賃料が基準となることが多い為、こちらに有利に交渉を進めることが可能となります。

2.交渉
いずれかの資料を用意しましたら、テナントに交渉していきましょう。
この交渉には、管理を自ら行っているのか、管理会社にお願いしているのか、で異なってきます。
(1)オーナーが自ら管理を行っている場合
この場合には、言うまでもありませんが、オーナー自らが、テナントと交渉する必要があります。
先に資料をいくつか掲載させていただきましたが、いきなり費用のかかる鑑定評価書を取得するのではなく、まずは、オーナー自らが(1)~(3)のいずれかの方法で、テナントに当たってみるべきです。
スムーズに賃料の増額が出来れば、それでいいですが、交渉の結果、増額に応じてくれそうもない場合に、鑑定評価書の取得を検討しましょう。
交渉をするテナントと過去にトラブル等があり、一筋縄ではいかないようなことが、予め分かっている場合には、時間を無題しない為にも、最初から鑑定評価書を取得することもご検討下さい。

(2)管理会社にお願いしている場合
管理会社に管理をお願いしている場合には、まずは、管理会社に相談してみましょう。
この際に、注意すべきは、契約内容です。
契約内容により様々ですが、賃料の増額をしても、管理会社に直接メリットがない場合(間接的には、賃料の増額により管理料は上がる可能性がありますが)には、積極的には応じてくれない可能性があることです。
このような相談に積極的に応じてくれるかどうか、管理会社が自発的に、増額交渉をしてくれるかどうか、で管理会社の質を見分けることが出来ます。
管理会社が、交渉に応じてくれない場合には、オーナーが自ら交渉するか、管理会社になんらかのインセンティブを与える必要があるでしょう。

3.交渉がまとまらなかった場合
交渉をして、テナントが賃料の増額に応じてくれなかった場合には、どうしたらいいでしょうか。
当たり前ですが、あきらめるか、更に、交渉を続けるかの2つしかありません。
今後、更に交渉を続ける場合には、時間と場合によっては裁判費用も必要となってきますので、賃料の増額によるメリット額と比較検討する必要があります。
今後も交渉を続ける場合には、当事者同士で、これ以上話し合っても、進展させることは難しいと思われますので、調停で話し合った方がいいでしょう。
調停でも、話しがまとまらなければ、次は、訴訟となります。