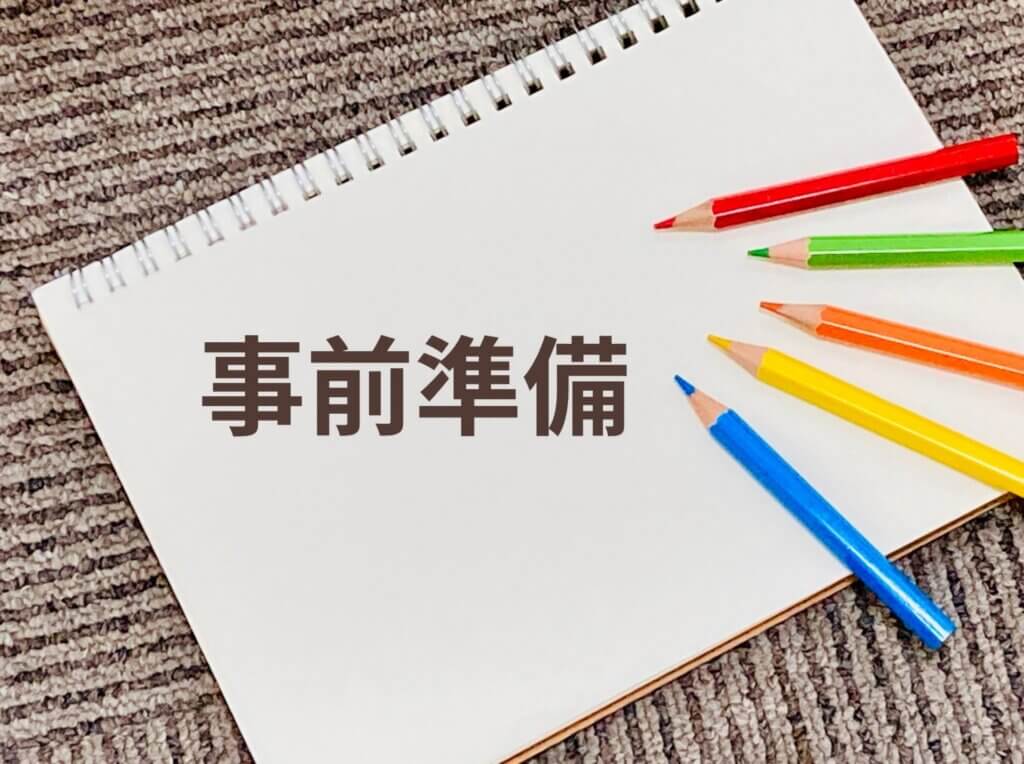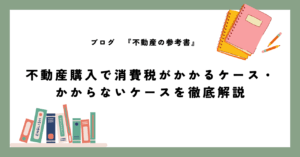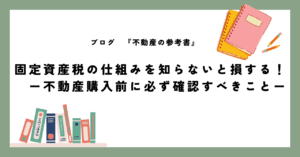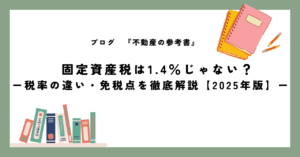不動産を売却しますと、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税のベースとなる譲渡所得金額は、以下のとおり計算されます。(譲渡所得税は、譲渡所得金額に税率を乗じて求められます。)
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除額 = 譲渡所得金額
収入金額は、売却価格となります。
取得費は、売却した不動産の購入代金です。
譲渡費用は、仲介手数料などです。
説明をしてしまえば、上記のとおりさらっと説明出来てしまいます。
各項目の詳細は、改めて、説明します。

ところで、取得費です。
タイトルに記載させていただいておりますが、取得費が不明な場合があるのだろうか、と疑問に思われたかもしれません。
重複しますが、売却価格である収入金額は、今回売却しましたので、その金額が分からないということはないでしょう。
譲渡費用も、同様に、今回の売却に際して、仲介手数料を支払っていると思いますので、この金額が分からない、ということもないでしょう。
では、取得費はどうでしょうか。
売却した不動産は、いつ取得されましたか。
5年前や10年前などであれば、売買契約書などが残っており、その売買契約書から取得費は分かるかと思います。
さらに、20年前、30年前となるとどうでしょうか。
売買契約書はありますか。
紛失してしまった、ということもあり得るでしょう。
なお、取得費が客観的に証明できればいいので、売買契約書でなくても大丈夫な場合があります。
例えば、銀行の通帳の支払金額で証明する、ということも考えられます。
では、さらに40年前、50年前となるとどうでしょうか。
取得の時期が古くなるほど、資料などの紛失の可能性も高くなり、取得費を証明するのは困難になります。
また、ご自身で売買で取得された場合にはいいですが、相続で取得した場合には、ますます困難になるのではないでしょうか。
では、取得費が不明な場合、どうしたらいいのでしょうか。
以下、取得費が不明な場合の対策について、説明致します。
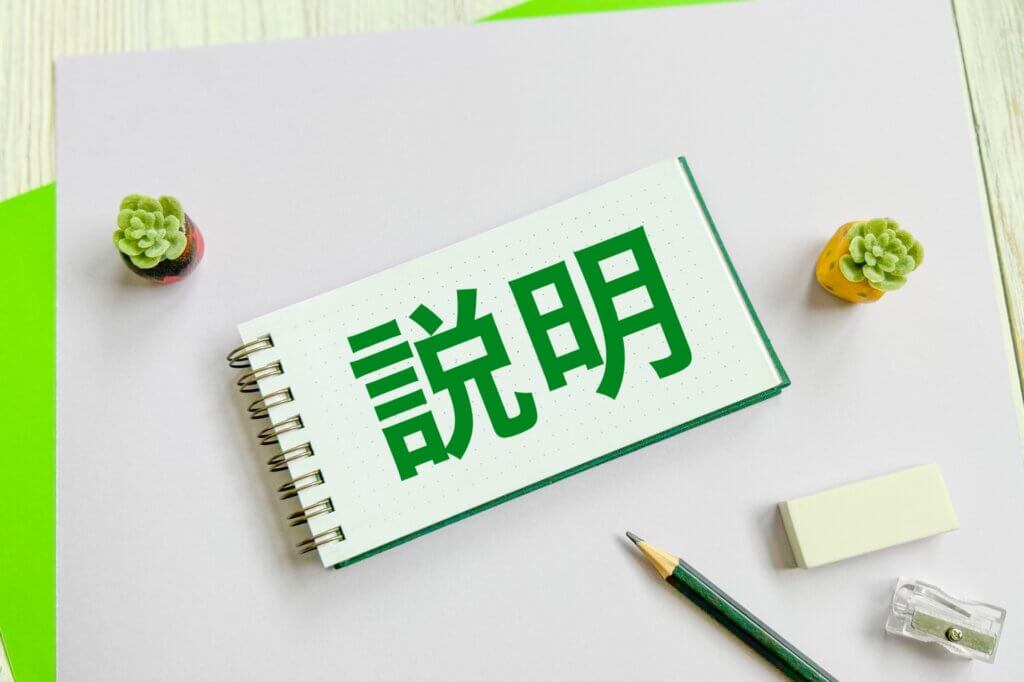
1 売却価格の5%
結論になりますが、取得費が分からない場合には、売却価格の5%を取得費とすることができます。
注意していただきたいのは、“することができる”でいうことです。
例えば、5,000万円で不動産を売却したのなら、250万円を取得費にすることが出来る、ということになります。
取得費が分からず、不安に思われていましたら、安心されましたでしょうか。
取得費が分からなくても、売却価格の5%を取得費とすることができますので、取得費に関する資料が見つからなくも、それ自体は、問題ありません。

なお、ブログタイトルに、対策3選とさせていただいておりますが、この5%については対策ではありません。
先の例をもう一度見ていただきたのですが、5,000万円で売却した不動産の取得費が250万円、ということに違和感は感じませんでしょうか。
取得の時期によって、一概には言えませんが、いくら昔であったとして、5,000万円で売却した不動産を250万円で購入出来たのでしょうか。
一般的な感覚として、不動産の価格が250万円というのは、いつの時代なのか、というぐらい時代錯誤な感じです。
つまり、売却価格の5%では、安すぎる、ということです。 そうしますと、この5%というのは、以下に説明させていただく対策が活用出来ない場合に、最後にやむなく使用する方法となります。
2 対策
それでは、以下の取得費が分からない場合の3つの対策を紹介致します。

(1)代わりの資料を探す
取得価格を証明する資料として、一番望ましいのは、売買契約書でしょう。
では、この売買契約書を紛失してしまったら、どうすればいいでしょうか。
まずは、売買をお願いした不動産業者に問合せてみることをお勧めします。
しかし、業者がすでになくなっている場合には、どうしようもありません。
また、隣人や知人から購入した場合には、そもそも契約書がないことも考えられます。 代わりの資料として、次のようなものが考えられます。
①重要事項説明書
売買金額が分かる資料として、重要事項説明書が考えられます。
ですが、売買契約書を紛失しているのでしたら、重要事項説明書も紛失している可能性も高いかもしれません。 また、先と同様に、隣人や知り合いから購入し、業者が介在していない場合には、重要事項説明書もありません。
②預金通帳
売買金額を振り込んだ預金通帳も証拠資料となる可能性があります。
③金銭消費貸借契約書
購入した時に、ローンを組んだのであれば、金銭消費貸借契約書があり、ここから購入金額が分かるかもしれません。
④分譲時パンフレット、チラシ
マンションでしたら、分譲時のパンフレットから購入価格が分かります。 新築戸建住宅や、マンションを含め中古物件の場合には、購入時のチラシから、購入価格を推測できます。
⑤登記事項証明書の乙欄
先の金銭消費貸借契約書と関連しますが、ローンを組んだ場合には、抵当権が設定されてますので、登記事項証明書の乙欄に借入額が記載されており、ここから購入価格を推測することも可能です。

(2)市街地価格指数
市街地価格指数とさせていただきましたが、相続税路線価、地価公示価格も利用できます。
併用してもいいかもしれません。
これらは、現在の価格(指数)と購入時の価格(指数)を比較して、取得費を推定する方法です。
昔の相続税路線価や地価公示価格は、国会図書館で入手できます。
最近のものは、インターネットで閲覧可能です。
なお、近年、市街地価格指数だけでは、否認されることが多いようですので、注意が必要です。
これは、当たり前のように思っています。市街地価格指数は、例えば、東京都区部などのようにエリアが漠然としていますので、購入物件の不動産価格を適切に示しているとは思えません。
相続税路線価と地価公示価格で補完すべきでしょう。
市街地価格指数で、もっとも注意いただきたいのは、当たり前といえば、当たり前なのですが、土地価格の指数になりますので、購入した物件が、戸建住宅やマンションなどの場合には、これらの価格を示す指数とはなっていないことです。 この点には、ご注意下さい。

(3)鑑定評価
3つめになりますが、鑑定評価を活用する方法になります。
先の市街地価格指数の場合には、土地のみとなりますが、鑑定評価でしたら、あらゆる不動産で対応可能となります。
しかし、この方法の最大の欠点は、鑑定評価料がかかることです。
更に、鑑定評価書を取得したからといって、必ずしも税務署に認められる訳ではないことにも注意が必要です。
また、鑑定評価も万能ではなく、一般に取得時期が古くなるほど、鑑定評価の精度も下がります。
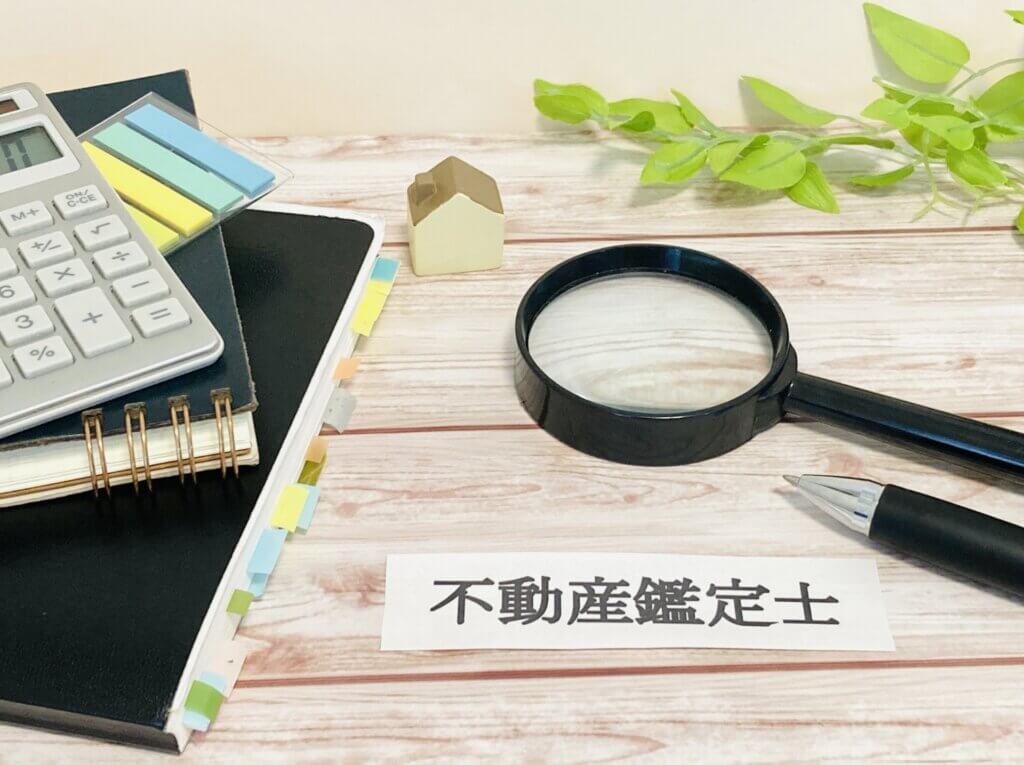
3 5%が得な場合もある
以上、3つの対策を紹介させてもらいました。
対策の前提として、売却価格の5%では、取得価格は安すぎるということで、話しを進めてきました。
しかし、反対に、5%の方が得な場合もあるのです。
一概には言えませんが、戦後など、かなり昔に取得した場合が該当します。 このような場合には、5%の方が有利となる可能性が高くなりますので、そのまま5%を活用した方がいいでしょう。
4 まとめ
取得価格が不明な場合の対策を説明させていただきました。
不動産鑑定士としては、鑑定評価の活用を是非検討してもらいたいところです。
なお、最後に一つ、鑑定評価を活用する場合に知っておいていただきたいことがあります。
確定申告に合わせて、手続きをすることになるかと思います。
ですが、確定申告の時期は、不動産鑑定の繁忙期になります。
従いまして、不動産鑑定をお願いしようと思っても、不動産鑑定士の方で、対応しきれない、ということが考えられます。
ですので、鑑定評価の活用を検討されている場合には、早めに対応されますことをお勧め致します。