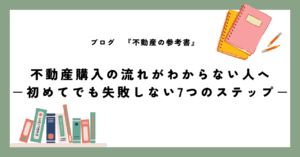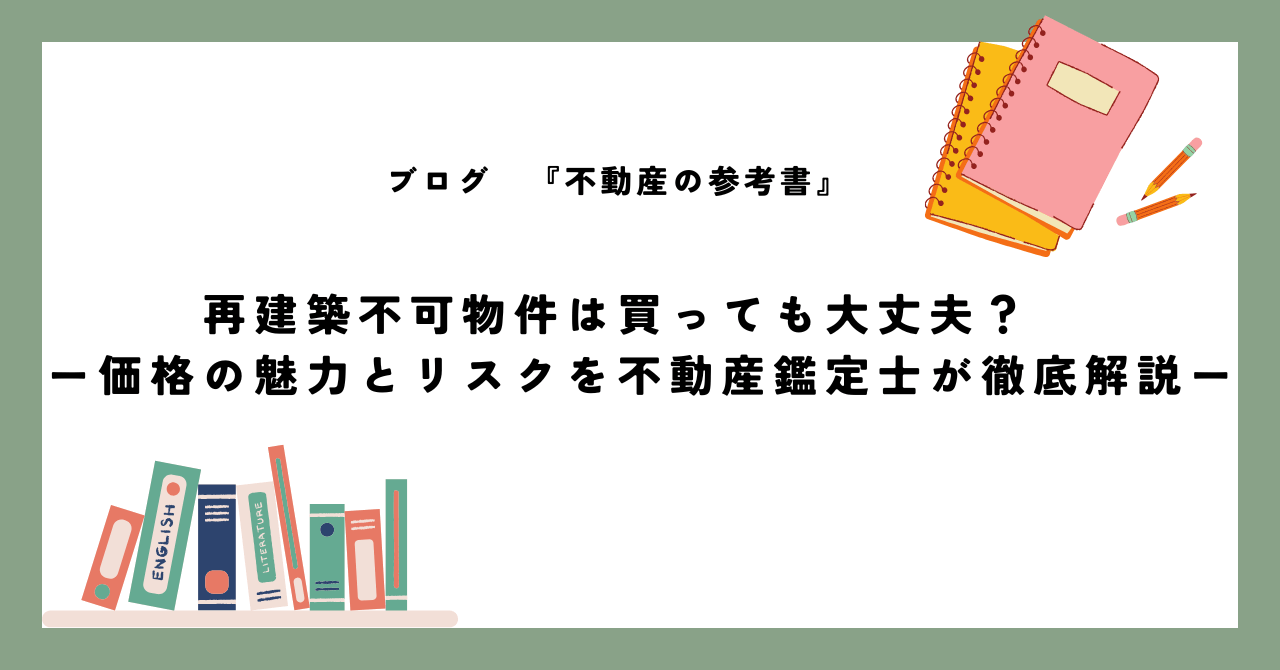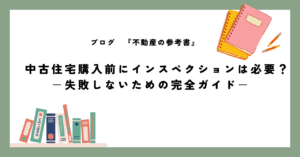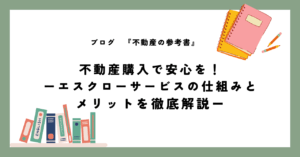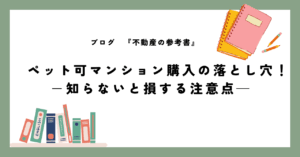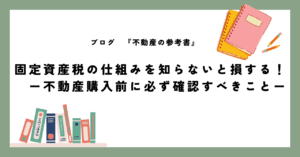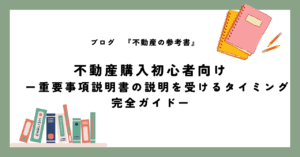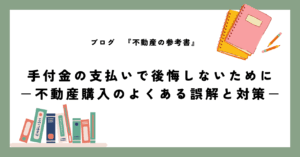はじめに|再建築不可物件が注目される背景
2020年代後半に入り、新築マンションや新築戸建住宅の価格高騰が続いています。特に都市部では、土地価格の上昇や建築資材の高騰、人件費の増加などが影響し、一般の購入希望者にとって新築物件の取得はますます難しくなっています。
こうした状況の中で、中古戸建住宅に目を向ける方が増えてきました。中古物件は新築に比べて価格が抑えられていることが多く、リフォームやリノベーションによって自分好みの住まいに仕上げることも可能です。
しかし、中古戸建を探していると、物件情報の中に「再建築不可」や「再建築不可物件」という表記を見かけることがあります。
初めてこの言葉を目にした方は、「え?建て替えできないってどういうこと?」と不安に感じるかもしれません。
実際、「再建築不可物件」はその名の通り、現在の建物を取り壊して新しい建物を建てることができない物件です。建て替えができないという制約は、一般的には大きなリスクと捉えられがちです。
しかし、再建築不可物件には価格の安さという大きな魅力もあります。条件次第では、一般の方でも十分に検討に値する選択肢となる可能性があります。
本記事では、不動産鑑定士の視点から、再建築不可物件の定義・仕組み・メリット・リスク・購入判断のポイントまでを徹底的に解説します。
「再建築不可物件は買っても大丈夫なのか?」という疑問に対して、専門的かつ実践的な視点でお答えしていきます。
このブログを読んで分かること
- 再建築不可物件の定義と再建築不可となる原因
- 購入時のメリットとデメリット
- 購入の判断基準と対策方法
- 専門家による見極めポイント
- 将来的な再建築可能性を含めた有効活用等

再建築不可物件とは?定義と基本知識
再建築不可物件とは?定義と基本知識
「再建築不可物件」とは、その名の通り、既存の建物を取り壊して新たに建て替えることができない物件を指します。
不動産の購入を検討している方にとって、「建て替えができない」という制約は非常に大きな懸念材料となるかもしれません。
では、なぜそのような物件が存在するのでしょうか?
その理由は、主に建築基準法に定められた「接道要件」を満たしていないことにあります。
建築基準法と接道要件の関係
建築基準法では、都市計画区域内において建物を建築するためには、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していることが求められます。これが「接道要件」です。
再建築不可物件は、以下のようなケースに該当することが多いです。
・前面道路が建築基準法上の道路ではない
例えば、私道や農道、里道などが該当することがあります。
・建築基準法上の道路に接している部分が2m未満
間口が狭いか、路地上敷地などで、道路との接面部分が狭い場合などに該当します。
このような条件下では、建物の建築許可が下りず、既存の建物を取り壊しても新たに建てることができないため、「再建築不可」とされるのです。
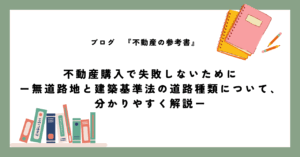
都市計画区域外では接道義務は適用されない
なお、都市計画区域外では、接道義務の規定が適用されないため、接道要件を満たしていなくても建築が可能です。
都市計画区域外の場合には、この建築基準法の接道義務の関係で再建築不可になることは、基本的にはないでしょう。
ですが、民法上の接道の問題もありますので、建築基準法の観点からは、再建築可能であったとしても、敷地に出入りできないようでは、土地利用が困難となりますので、この点には注意して下さい。
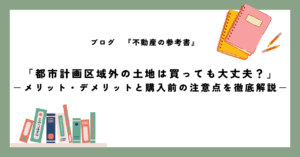
再建築不可物件は「違法建築」とは限らない
誤解されがちですが、再建築不可物件は違法建築とは限りません。
あくまで「建て替えができない」という制約があるだけで、現在の建物が、建築時に合法的に建てられたものであれば、居住や使用には問題ありません。
これを、少し難しい文言になりますが、既存不適格建築物といいます。
一方で、初めから違法となっている建物もあるかと思いますので、先の既存不適格建築物とは区別して下さい。
いずれにしましても、老朽化が進んだ場合に建て替えができないため、長期的な資産価値や安全性には注意が必要です。
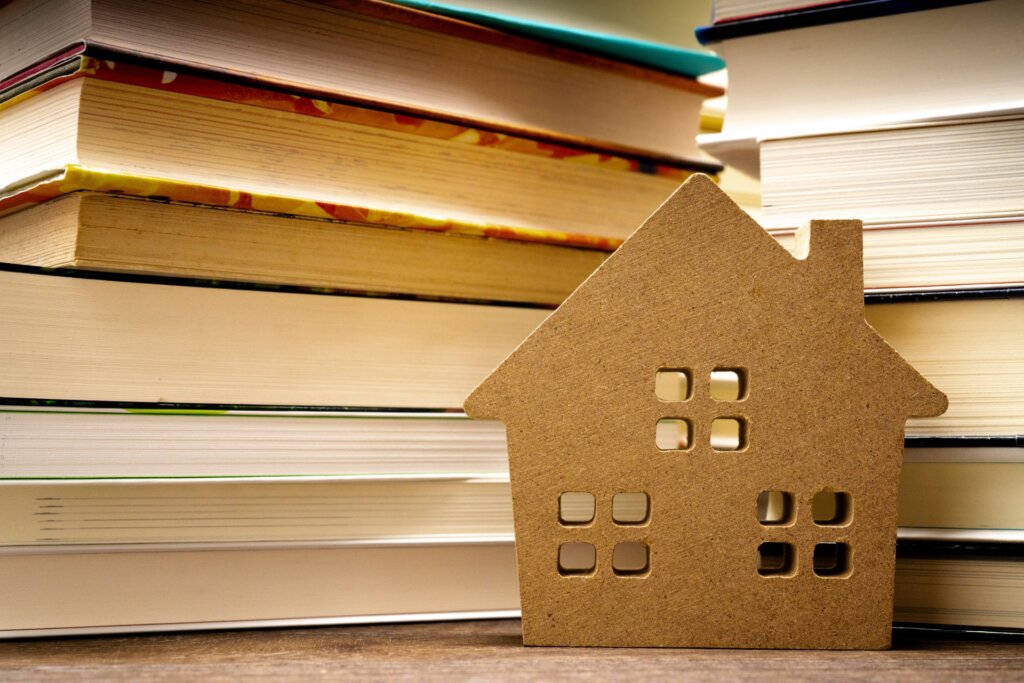
再建築不可物件のメリットと魅力
今までの説明で、再建築不可物件にマイナスの印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれませんが、再建築不可物件ならではのメリットもありますので、以下説明していきます。

再建築不可でも魅力はある?価格の安さが最大のメリット
再建築不可物件は「建て替えができない」という制約があるため、一般的には敬遠されがちです。
しかし、その分価格が大幅に安く設定されていることが多く、予算を抑えたい方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。
例えば、同じエリア・同じ広さの再建築可能な物件と比較すると、2〜5割程度安く購入できるケースも珍しくありません。
これは、建て替え不可という制約が資産価値に影響するため、売主側が価格を下げて販売しているためです。
固定資産税も安くなる可能性
再建築不可物件は、資産評価額が低くなる傾向があるため、固定資産税が安くなる可能性があります。
特に築年数が古く、建物の評価額がほぼゼロに近い場合には、土地の評価額のみが課税対象となり、年間の維持コストを抑えることができます。
これは、長期的に住む予定の方や、セカンドハウスとして利用したい方にとっては大きなメリットです。
投資用・収益物件としての活用も可能
再建築不可物件は、賃貸物件として活用することも可能です。
建て替えはできなくても、現状の建物をリフォーム・リノベーションすることで、賃貸需要に応えることができます。
特に、以下のようなケースでは収益性が見込めます:
- 立地が良く、賃貸ニーズが高いエリア
- 建物の状態が良好で、最低限の改修で入居可能
- 初期投資額が低いため、利回りが高くなる
ただし、建物の老朽化や修繕費用の見積もりは慎重に行う必要があります。
また、融資を受けることは、一般的にはハードルが上がりますので、自己資金での投資とならざるを得ないでしょう。
「住めればいい」という割り切りができる人には最適
再建築不可物件は、「建て替えなくても、今の建物で十分」という価値観を持つ方にとっては、非常に合理的な選択肢です。
特に以下のような方には向いています:
- 単身者や夫婦2人など、広さを求めない層
- リノベーションに興味があり、古民家風の住まいを楽しみたい方
- 一時的な住まいやセカンドハウスを探している方
価格の安さを活かして、立地や周辺環境を重視した物件選びができるのも魅力の一つです。
再建築不可物件のデメリットと注意点
メリットと魅力がある一方で、当然、デメリットと注意点もありますので、こちらについても、しっかりと把握しておいて下さい。
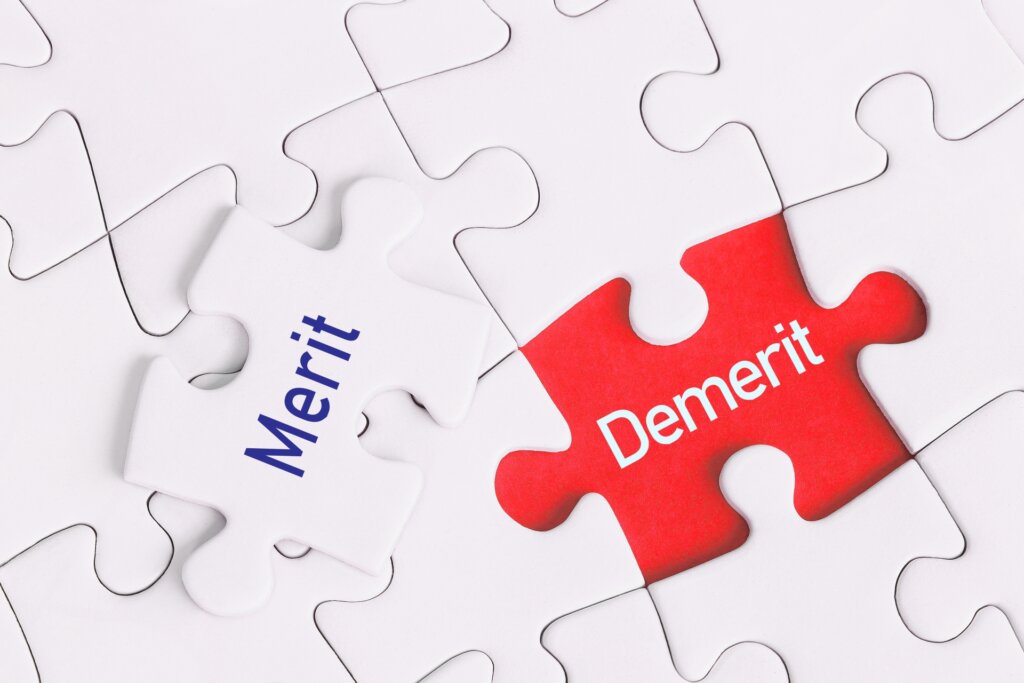
建て替え不可による資産価値の低下
再建築不可物件の最大のデメリットは、将来的な資産価値の低下です。
建物が老朽化しても、建て替えができないため、物理的にも経済的にも再生が難しいという問題があります。
特に、築年数が古くなるにつれて、建物の評価額は下がり、土地の価値も「再建築不可」という制約により市場価値が低くなる傾向があります。
これは、将来的に売却を考えている方にとっては大きなリスクです。
融資が通りにくい(住宅ローンの制限)
再建築不可物件は、金融機関からの評価が低くなるため、住宅ローンの審査が通りにくいという問題があります。
特に以下のようなケースでは注意が必要です:
- 銀行が担保価値を認めない
- フルローンが組めない
- 金利が高くなる可能性がある
そのため、現金購入が前提となる場合も多く、資金計画に余裕が必要です。
売却時の流動性の低さ
再建築不可物件は、購入希望者が限られるため、売却時に買い手が見つかりにくいというデメリットがあります。
特に一般の購入者は「建て替えできない=使いにくい」と判断するため、売却までに時間がかかることが多いです。
また、価格交渉においても、買い手側がリスクを重視するため、希望価格での売却が難しいケースもあります。
建物の老朽化と修繕費用の負担
建て替えができないということは、既存の建物を維持し続ける必要があるということです。
築年数が経過すると、以下のような修繕が必要になる可能性があります:
- 屋根や外壁の補修
- 給排水設備の交換
- シロアリ対策や耐震補強
これらの修繕費用は、建て替えよりも割高になることもあり、長期的な維持コストがかさむ可能性があります。
増改築にも制限がある
再建築不可物件では、増築や大規模な改築も制限される場合があります。
建築確認申請が必要な工事は、接道要件を満たしていないと認可されないため、自由な間取り変更や設備更新が難しいこともあります。
そのため、リノベーションを前提に購入を検討している方は、事前に自治体や建築士に相談することが重要です。
再建築不可物件は買っても大丈夫?判断基準と対策
-「価格の安さ」だけで決めない!購入判断のポイント-
再建築不可物件は、価格の安さが魅力ですが、安いからといって即決するのは危険です。
購入を検討する際には、ライフプラン・資産価値・将来の活用方法など、複数の視点から慎重に判断する必要があります。
以下のような基準をもとに、購入の可否を検討しましょう。

住み続ける期間と家賃相当額の比較
一つの判断材料として、住み続ける期間と家賃相当額の比較があります。
例えば、同じエリアで賃貸物件に住んだ場合の家賃を計算し、それを購入価格と比較することで、経済的に合理的かどうかを判断できます。
例:
- 購入価格:800万円
- 同エリアの家賃:月8万円
- 住み続ける予定:10年(家賃総額=960万円)
この場合、購入の方が経済的に有利と判断できます。
他に、仲介手数料や税金などもかかりますのので、上記はざっくりとした目安と捉えて下さい。
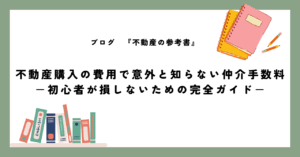
隣地購入による再建築の可能性
再建築不可の原因が「接道幅2m未満」である場合、隣地を購入することで接道幅を2m以上に広げ、再建築可能にする方法があります。
この方法は、以下の条件を満たすと実現可能です。
- 隣地が空き地または売却可能な状態
- 隣地所有者との交渉が可能
このようなケースでは、将来的な資産価値の回復も期待できるため、積極的に検討する価値があります。
隣地所有者に売却するという選択肢
逆に、隣地所有者に自分の物件を売却するという選択肢もあります。
例えば、隣地所有者も再建築不可で、土地を取得することで、接道幅が広がり、再建築が可能となる場合には、相場より高く買ってくれる可能性もあります。
このような交渉をスムーズに進めるためには、日頃から隣地所有者との関係を良好に保つことが重要です。
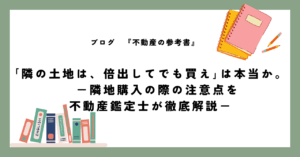
前面道路が建築基準法の道路でない場合の対策
前面道路が建築基準法の道路でない場合でも、将来的に建築可能になる可能性があるケースも存在します。
例えば、以下のような状況が該当します:
- 道路の位置指定申請が可能
- 周辺の開発計画により道路整備が進む
- 行政との協議により、道路認定が得られる
このような場合には、土地の価値が将来的に上昇する可能性があるため、購入時にその見込みを調査することが重要です。
不動産鑑定士や建築士への相談は必須
再建築不可物件の購入を検討する際は、不動産鑑定士や建築士などの専門家に相談することが不可欠です。
専門家は、以下のような視点からアドバイスをしてくれます:
- 再建築可能性の有無
- 土地の資産価値評価
- 法的・技術的な制約の確認
- リフォーム・修繕の可否と費用
専門的な視点を取り入れることで、後悔のない購入判断が可能になります。
不動産鑑定士が教える!再建築不可物件の見極め方
-専門家の視点で見る「再建築不可物件」の建築可能性と価値-
再建築不可物件は、一般の方にとって判断が難しい物件です。
しかし、不動産鑑定士の視点を取り入れることで、リスクと可能性を冷静に見極めることができます。
鑑定士は、単に「建て替えができない」という表面的な情報だけでなく、土地の潜在的価値や将来的な再建築可能性、周辺環境との関係性などを総合的に評価します。

再建築可能性の調査ポイント
再建築不可物件でも、将来的に再建築が可能になるケースがあります。
鑑定士が確認する主なポイントは以下の通りです。
接道状況の詳細確認
- 道路の種類(建築基準法上の道路かどうか)
- 接道幅の実測値
前面道路は建築基準法の道路であるのかどうかにより、再建築可能性の難易度が異なってきますので、とても重要な確認事項です。
周辺の開発状況
- 道路整備計画の有無
- 近隣の建築事例
- 行政との協議履歴
現況は、前面道路が建築基準法の道路に該当していなくても、同一道路沿いの地権者と協議をして、将来的に4m以上の幅員を確保するというような同意を取れれば、建築が可能となることもあります。
これについては、下記のブログを参考にして下さい。
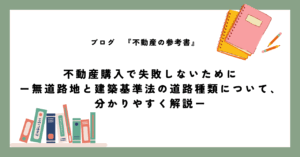
現況は、未接道等により、建築不可能であっても、一体をマンション用地としてデベロッパーが購入してくれるかもしれません。
この場合には、再建築をする訳ではありませんが、購入した時の価格よりも、高い価格で売却出来る可能性があります。
隣地との関係性
- 境界の明確性
- 隣地購入の可能性
- 隣地所有者の意向
これらの情報をもとに、「今は再建築不可でも、将来的に可能性があるかどうか」を判断します。
隣地を買収できれば、接道義務を満たせる可能性があります。
見方を変えれば、隣地の買収に要する費用を見込んだぐらいの金額でなければ、未接道の土地は買えない、ということにもなります。
土地の資産価値評価
再建築不可物件でも、土地そのものに価値がある場合があります。
鑑定士は、以下のような観点から土地の評価を行います:
- 立地(駅距離・商業施設・学校など)
- 土地形状(整形地かどうか)
- 周辺相場との比較
- 利用可能性(賃貸・駐車場・倉庫など)
特に、再建築不可でも収益化できる土地であれば、投資対象としての価値も見込めます。
駐車場や資材置場としての利用が、主な利用方法になるでしょう。
最近では、バイク置場としての利用も需要があります。
法的・技術的な制約の確認
鑑定士は、建築基準法だけでなく、都市計画法・条例・地域指定などの法的制約も確認します。
また、建物の構造や老朽度、耐震性などの技術的な側面も評価対象です。
これにより、リフォームの可否や安全性、維持コストなどを事前に把握することが可能になります。
購入判断に役立つ「鑑定評価書」の活用
不動産鑑定士による「鑑定評価書」は、物件の価値を客観的に示す資料として非常に有効です。
特に以下のような場面で役立ちます:
- 金融機関への融資相談
- 売買価格の妥当性判断
- 相続や財産分与の場面
- 将来的な売却時の交渉材料
再建築不可物件の購入を検討する際は、鑑定評価書を取得しておくことで、安心して意思決定ができるようになります。
まとめ
-再建築不可物件は「安さ」だけで判断しない-

安さの裏にあるリスクと可能性を見極める
再建築不可物件は、確かに価格の安さという大きな魅力があります。
しかし、その裏には「建て替え不可」「資産価値の低下」「融資の制限」など、見逃せないリスクが潜んでいます。
一方で、条件次第では「隣地購入による再建築可能化」や「収益物件としての活用」など、将来的な可能性を秘めた物件でもあります。
一般の方でも購入可能なケースはある
再建築不可物件は、これまで「プロ向け」「投資家向け」とされてきましたが、最近では一般の方でも購入を検討するケースが増えています。
特に以下のような方には、選択肢として十分に検討する価値があります:
- 予算を抑えてマイホームを持ちたい方
- リノベーションに興味がある方
- 一時的な住まいやセカンドハウスを探している方
- 賃貸運用を視野に入れている方
ただし、購入前には専門家の意見を必ず取り入れることが重要です。
購入前に確認すべきチェックリスト
最後に、再建築不可物件を検討する際に確認すべきポイントをまとめておきます:
- 接道要件を満たしているか(建築基準法上の道路か/接道幅2m以上か)
- 都市計画区域内か区域外か
- 隣地購入や道路整備の可能性はあるか
- 建物の状態(老朽化・修繕履歴・耐震性など)
- 融資の可否(住宅ローンが使えるか)
- 将来的な売却や賃貸の可能性
- 不動産鑑定士・建築士など専門家の意見を得ているか
このチェックリストをもとに、「安さ」だけでなく「将来性」「安全性」「資産性」も含めた総合的な判断を行うことが、後悔しない不動産購入につながります。
不動産購入に際しては、どのように進めればよいか分からないことも多いかと思います、これについては、下記のブログでまとめていますので、よければ参考にしてみて下さい。