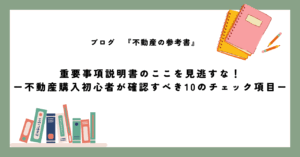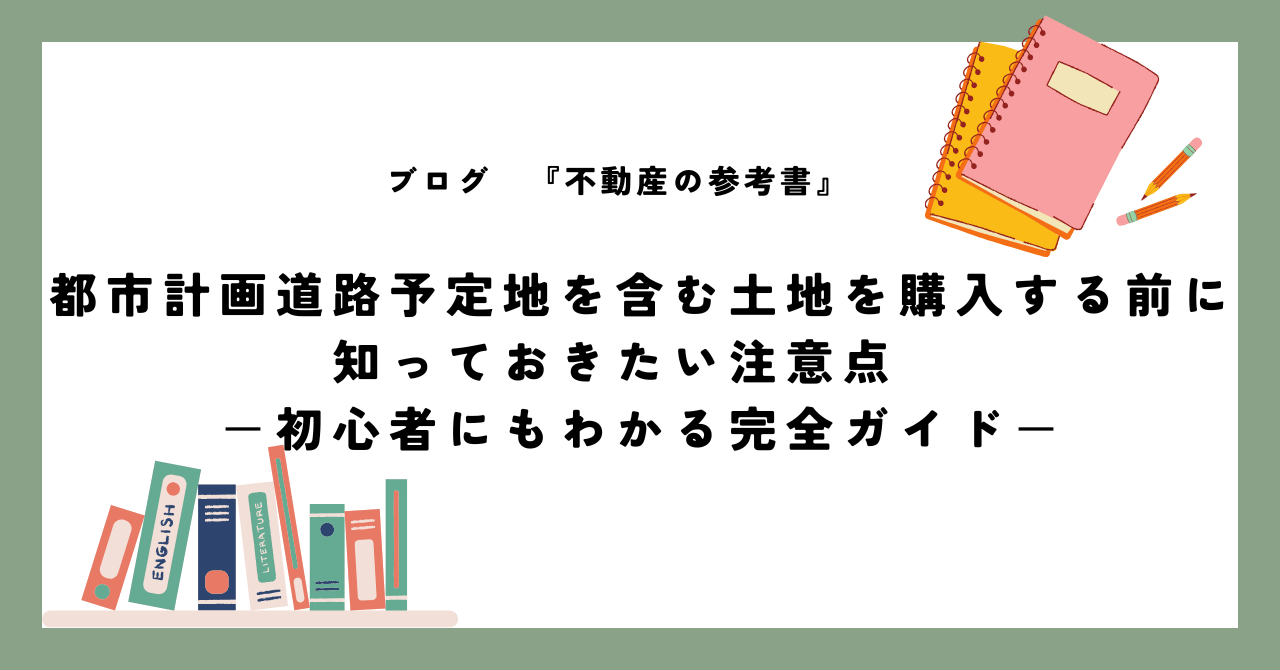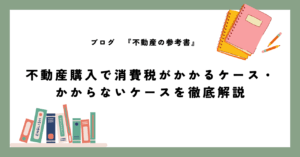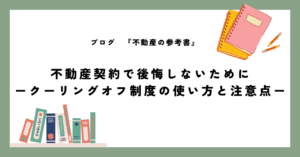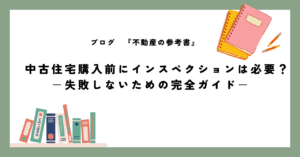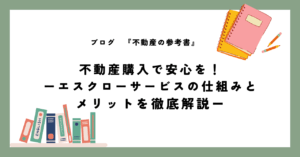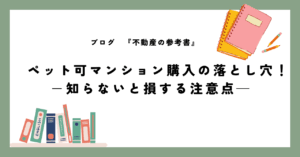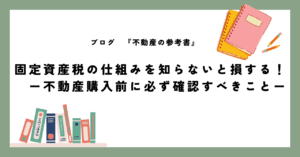都市計画道路という言葉を聞いたことはありますか
都市計画道路という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
不動産に関連する仕事をされている方でしたら、当然ご存じでしょう。
また、宅建を受験されたことがある方も、きっとご存じのことと思われます。
言葉どおりで、都市計画(都市計画法)で定められた道路という意味ですが、通常、都市計画道路という時には、これから整備される道路のことを意味していることが多いです。
都市計画道路に指定され、道路整備が完了しても、その道路は都市計画道路に違いはありませんが、完成している場合には、その道路に対して、敢えて、都市計画道路という言うことは少ないと思います。
これから整備される訳ですから、現状の道路が拡幅されることによって整備される場合には、イメージも湧きやすいですが、全く道路がないような場所に都市計画道路の計画があったりすることも多く、こんな所に道路が出来るのか、と驚かれることもあるでしょう。
不動産に馴染みのない方が、都市計画道路に直面する場合として想定されるのは、購入しようとしている土地、土地付建物が、都市計画道路予定地を含んでいる場合でしょうか。
購入をする場合でなくても、古くからお住まいの家の土地が、都市計画道路に指定されている、ということもあり得ます。
以下、都市計画道路について、解説するとともに、その注意点等についても触れていきます。

このブログを読んで分かること
- 都市計画道路の基本的な意味と仕組み
- 予定地を含む土地購入時の確認方法
- 計画決定段階と事業決定段階の違い
- 建築制限の内容と影響
- プラス要因・マイナス要因の考え方
- 行政による買収と既存不適格のメリット
都市計画道路とは
先に、簡単に触れましたが、都市計画道路とは、都市計画法によって定められた道路です。
都市施設の一種で、都市施設には、他に、公園、河川(堤防)などがあります。幅員20m、30m等の幹線道路となっていることが多いです。
確認方法
都市計画道路に該当するかどうかは、市区町村役場の都市計画課にて、確認することが出来ます。
例えば、調べている土地がまるまる都市計画道路予定地に該当する場合を除き、通常は、土地の一部が都市計画道路予定地に該当することが多いです。
この場合に、役所で調査すると、例えば、”現在の道路から1.5mまでの範囲が都市計画道路予定地となります”、などの回答となります。
敷地の一部が都市計画道路予定地になってしまうと、その部分は将来、道路になりますので、利用できません。
一見するとこれは大問題ですが、デメリットばかりではないのです。この後、説明していきますので、どうぞ最後まで読み進めて下さい。

確認に際しての注意点
ここで注意していただきたいのは、先の例で言いますと、1.5mの詳細です。
役所では、図面をもとに回答をしてくれますが、都市計画道路事業の進行状況によっては、現地での測量が行われていないこともあり得ます。
そうすると、図面からの概測になりますので、将来的に誤差が生じる可能性があります。
そこで、先の例で云うと、1.5mという回答であったとしても、詳細は、都市計画道路予定地は1.0mの範囲内であるが、誤差を考慮して(誤差を0.5m加味して)、1.5mという回答が得られることがあります。
ですので、単に、どの程度都市計画道路予定地に該当するかだけではなく、誤差も含んでいるのかどうかも、確認する必要があります。
また、この後、説明致しますが、計画決定段階か、事業決定段階で、規制なども異なるので、これについても合わせて確認する必要があります。
都市計画道路に該当するとどうなるか
それでは、実際に都市計画道路予定地を含む場合に、どのようになるのか、具体例、図解を交えて、解説していきます。
具体例
よくあるケースとしては、敷地前面の道路が都市計画道路に指定されており、道路拡幅が必要で、敷地の一部が都市計画道路に該当する場合だと思われます。
ここでは、土地の購入を検討しており、購入予定の土地の一部が都市計画道路に該当する場合を例に説明します。
図解すると、以下のようになります。
まず、図の左側を見ていただきたいのですが、200㎡の土地があり、道路幅員が10mだったとします。この道路が、20mの都市計画道路に指定されており、対象地側に5mの後退が必要だったとします。
そうすると、全体で200㎡あった土地のうち、50㎡が都市計画道路予定地となります。
都市計画道路予定地のイメージは、このとおりです。
では、この道路予定地は、どうなるのでしょうか。
結論としましては、利用に当たり制限はありますが、予定地そのものは行政にて、買いっとってもらえますので、心配は無用です。
規制の内容
ここで少し考えていただきたいのですが、先の都市計画道路予定地ですが、いずれ買い取ってもらえるとして、それまではどうなるのでしょうか。
これは、計画決定の段階か、事業決定の段階かで異なってきます。
少し難しなってきたかもしれませんが、丁寧に説明していきますので、安心して読み進めて下さい。
以下、それぞれについて説明します。
計画決定の段階
計画決定の段階では、名前のとおり、計画として決まっているだけで、実際に事業が行われている訳ではありません。また、いつ事業が行われるのかは、未定の場合も多いです。
用地買収が進んでいない場合には、現地を見ても、こんなところに道路が出来るのか、あるいは、道路が拡幅されるのか、と思われることもあるかもしれません。
従って、このような段階で、あまり厳しい規制を設けますと、土地所有者は大きな不利益を被ることになります。
その一方で、都市計画道路事業を行う側からしますと、いずれ道路になる土地に、高層の建物などは建てて欲しくはありません。
よって、計画決定の段階では、木造、鉄骨造等で、地階がなく、3階且つ高さ10m以下の建物でしたら、都市計画道路予定地にも建物を建てることが出来ます。
そうしますと、住宅地などで、木造2階の建物を建てる場合には、建築上は、都市計画道路の影響は受けないことになります。

事業決定の段階
都市計画道路の「事業決定段階」とは、計画が単なる構想ではなく、実際に工事を行うことが正式に決まった状態を指します。
イメージとしては、まず、先の計画決定段階を経て、この事業決定段階となります。工事が始まりますので、道路が出来ることが目に見えて分かるようになります。
この段階では、道路整備のための事業が進行しているため、都市計画道路予定地に建物を建てることは原則として禁止されています(例外もありますが、通常は建てられないものと理解して下さい。)。
なぜ禁止されるのでしょうか?
理由は明確で、都市計画道路予定地は将来的に道路になる土地だからです。もしこの土地に新しい建物を建ててしまうと、道路工事の妨げになり、事業の進行に大きな支障が出ます。行政としても、道路整備を円滑に進めるため、建築を制限する必要があります。

都市計画道路は、プラスかマイナスか
先の例でいいますと、敷地の一部が道路予定地になりますので、都市計画道路予定地を含むことは、マイナス要因のように思われるかもしれません。
しかし、マイナス要因ばかりでなく、プラスの要因もあるのです。
プラス要因とマイナス要因のそれぞれについて、以下説明していきます。

プラス要因
まず、プラス要因として考えられるのが、将来的には、道路が拡幅することですね。また、都市計画道路の配置状況によっては、新しく道路が出来るということもあるでしょう。
これは、明らかにプラス要因です。
そして、かならずプラス要因となる訳ではないのですが、場合によってはプラス要因となるものがあります。
この場合によって、プラス要因となるのが、既存不適格なのですが、これは、次の章で詳しく解説します。
マイナス要因
マイナス要因として、真っ先に思いつくのは、道路予定を含むことそのものがマイナスのように思われるかもしれません。
しかし、道路予定地は、行政が買い取ってくれますので、道路予定地を含むからと云って、必ずしも減価となる訳ではありません。
では、どのような場合に減価となるのでしょうか。
少し難しい言い方になりますが、理論的にいいますと、鑑定用語になりますが、最有効使用が出来ない場合に、減価要因となります。
例えば、高容積の地域で、高層のビルが建ち並ぶ商業地域だった場合に、都市計画道路予定地は、木造、鉄骨造の3階建の建物しか建築できない為、容積率を消費出来ない場合が考えられます。
このような場合には、都市計画道路による影響(制限)を受けている訳ですから、マイナス要因となってしまいます。
また、道路予定地を買い取ってもらえると云っても、残った土地で有効利用出来ない場合にも、減価となるでしょう。
一方で、木造2階の建物を建てるのが標準的な地域であれば、実質的には、制限を受けない訳ですから、影響がないとも言えるでしょう。
以上により、都市計画道路のマイナスの影響は、個別の土地の状況によって、異なってきます。

都市計画道路がプラスとなる場合
前記では、結果的に、減価となる場合について、考察しましたが、プラスとなる場合は、あるのでしょうか。
実は、あるのです。
言葉だけだと難しいので、数値も使って説明します。
先の図を見ていただきたいのですが、容積率が200%だったとします。土地は、200㎡ですので、建築可能な延床面積は、400㎡となります。
ですので、延床面積400㎡の建物を、都市計画道路予定地外に建てます。
都市計画道路事業が進行して、道路予定地が買収されると、土地面積は、150㎡となります。
容積率が200%ですから、150㎡の土地には、本来であれば延床面積300㎡の建物しか建てられませんが、400㎡の建物が建っていることになります。一見、容積率オーバーで違反のように思えます。
この状態を既存不適格といいます。
建築した時には、適法であり、その後、法律の変化により、法律を満たさなくなった場合のことを言います。
これは、違反ではありません。
よって、道路予定地部分は、買ってもらえ、残った土地には、本来建てられない規模の建物が存しているということになり、これはプラスとなります。
このように、必ずしもプラスになるとは限りませんが、都市計画道路の影響は、それぞれのケース毎に、検討することが重要になってきます。

まとめ
以上、都市計画道路について説明しました。
都市計画道路予定地を含む、となると驚かれるかもしれませんが、不動産の実務を行っている方でしたら、よくある話しですなので、それ程、驚くことではありません。
説明させていただきましたとおり、都市計画道路予定を含むということに驚くのではなく、それがプラスになるのかマイナスになるのか、また、道路予定地を含むことによる影響を踏まえた有効利用を積極的に考え欲しいです。
なお、都市計画道路予定地を含む土地を売買する場合には、公有地の拡大の推進に関する法律の届け出が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。